- 「出題範囲が似てるから一緒に勉強すれば効率的なんじゃないか」
- 「どうせなら今年中にダブル合格してしまいたい」
- 「知り合いが両方合格してたから、自分にもできるはず」
そう考えて、宅建士と賃貸不動産経営管理士のダブル受験を検討していませんか?
確かにどちらも不動産業界で評価の高い資格で、同時取得できれば大きな武器になります。
しかし、ここに“見えない落とし穴”が…。実は安易なダブル受験は、勉強効率を下げ、どちらの合格も遠ざけてしまう可能性が高いのをご存知でしょうか。
この記事では、ダブル受験のリスクや難しさを具体的に解説し、失敗を避けるために「どちらを優先すべきか」「効率的な学習順序」をお伝えします。
結論から言うと、まずは宅建士から取得するべきです。なぜ宅建士を先に取るべきなのか、その理由と最短で資格を揃える戦略を詳しくご紹介します。
宅建士と賃貸経営管理士、それぞれの資格の違いとは?
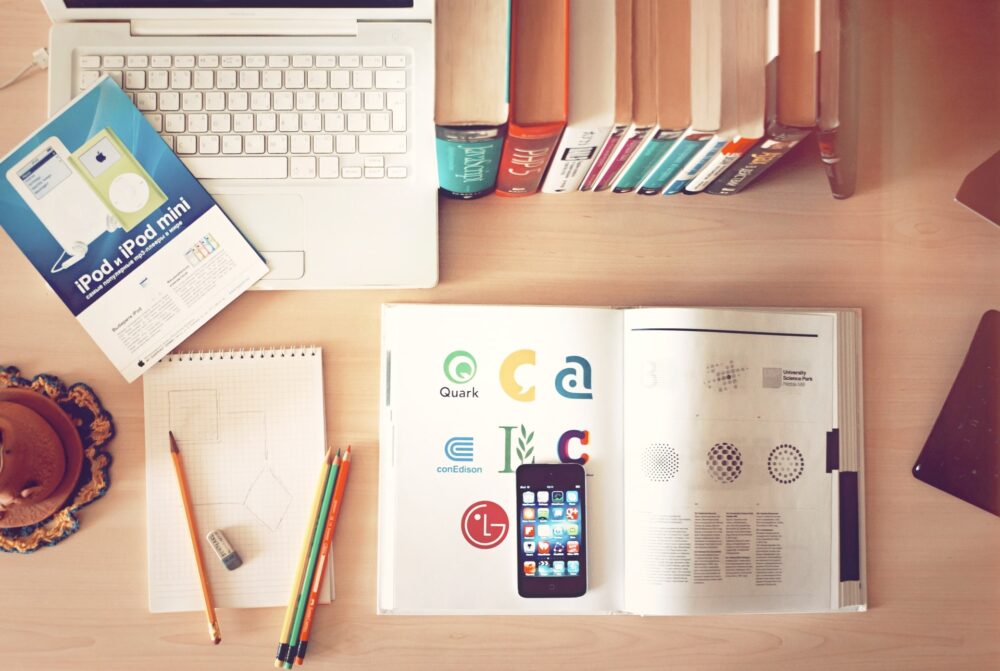
宅地建物取引士(宅建士)とは?
宅建士は不動産取引において「重要事項説明書の説明」「契約書への記名押印」といった独占業務を持つ国家資格です。不動産会社には必ず宅建士が在籍していなければならず、そのニーズは常に高いので不動産資格の中では一番人気のある資格です。
- 試験時期:10月第3日曜日
- 出題形式:50問/四肢択一
- 合格率:約15〜17%
- 主な出題範囲:権利関係、法令上の制限、宅建業法、税・その他

宅建は不動産資格の中でいちばん人気がある資格♪
賃貸不動産経営管理士とは?
賃貸不動産経営管理士は、主に賃貸物件の管理運営に関する知識を問われる資格です。2007年から始まった民間資格でしたが2021年から国家資格化され、「業務管理者」になるための要件のひとつとなりました。
第十二条 賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、一人以上の第四項の規定に適合する者(以下「業務管理者」という。)を選任して、当該営業所又は事務所における業務に関し、管理受託契約(管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の内容の明確性、管理業務として行う賃貸住宅の維持保全の実施方法の妥当性その他の賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸に係る事業の円滑な実施を確保するため必要な国土交通省令で定める事項についての管理及び監督に関する事務を行わせなければならない。
出典:e-Gov法令検索「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第十二条」
- 試験時期:11月第3日曜日
- 出題形式:50問/四肢択一
- 合格率:20〜40%(ただし年々難化傾向)
- 主な出題範囲:民法、建築・設備、賃貸管理実務、賃貸借契約、法令

国家資格化されたことによって人気が高まってきました!
ダブル受験をおすすめしない理由

出題範囲が被っているようで「深さ」が違う
一見、宅建士と賃貸経営管理士は出題範囲が似ているように思えますが、実はそれぞれに独自の論点があり、片方の知識だけでは太刀打ちできません。
- 宅建士
- 「宅建業法」「権利関係」など、法律的な重厚な問題が中心。
- 賃貸不動産経営管理士
- 「建物管理」「設備管理」など、実務寄りの知識が多く問われる。

共通範囲もありますが、試験の難度や傾向が異なるため、片手間では合格が難しい!
試験時期が近すぎて準備が中途半端になる
- 宅建士試験:10月の第3日曜日
- 賃貸不動産経営管理士試験:11月の第3日曜日
1ヶ月しかないこの期間で、片方の試験の疲労を回復しながらもう一方に完全シフトするのはかなりの負担です。しかも、どちらも50問という本格的な試験。両試験とも本気で臨むには、かなりの学習計画と体力が求められます。

両試験の期間が1ヶ月しかないので厳しいスケジュールになってしまいます。
どちらも「片手間」で受かる試験ではない
「ダブル受験=効率が良い」と思いがちですが、実はどちらの試験も近年レベルが上がっており、対策なしでは簡単に落ちてしまいます。
- 宅建士は約20万人が受験し、合格率はたったの15%前後
- 賃貸経営管理士も国家資格化後、年々難しくなり合格率は下がりつつある。
1つの試験に集中しても合格することが難しいのに、両試験を一度にこなすのは「戦略的」ではなく「無謀」と言えるかもしれません。

どちらも中途半端な学習になってしまうかも。
賃貸経営不動産管理士の難問化
かつては「宅建より簡単」と言われていた賃貸不動産経営管理士試験。しかし、2021年の国家資格化をきっかけに試験内容が徐々にレベルアップしています。
- 法律問題が本格化(民法・借地借家法など)
- 実務に関する知識がより具体的に問われる
- 過去問の使い回しが減り、新傾向の出題が増加
- 暗記だけでは通用しない思考力を問う問題も登場
2023年試験では、「実務的な管理業務」や「専門用語の正確な理解」を問う難問が多数見られました。今後もこの傾向は続くと予想され、「とりあえず宅建が終わったら受けてみよう」という軽い気持ちでは合格できない資格になりつつあります。

賃貸不動産経営管理士は“簡単な資格”ではなくなってきています。
業務管理者は宅建士でもなれる
賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所ごとに、一人以上の「業務管理者」の配置を義務付けられており、以下の要件を満たせば「業務管理者」になることができます。
業務管理者の要件
- 賃貸不動産経営管理士+2年以上の実務経験
- 宅建士+指定講習+2年以上の実務経験
つまり、どちらも「2年以上の実務経験」は必要ですが、宅建士でも業務管理者になれるといることです。ちなみに2025年時点では賃貸経営不動産管理士には独占業務はありません。
賃貸経営管理士は不動産業務、実務に役立つ資格で、将来的に独占業務が増えていく可能性はありますが「資格を取得して恩恵を得たい」と考えるのであれば宅建士の方がよいでしょう。

賃貸不動産経営管理士には“独占業務”がないことに注意!
宅建士と賃貸経営不動産管理士の難易度を徹底比較

「結局どっちが難しいの?」この疑問は、ダブル受験を考える人がまず気になるポイントではないでしょうか。ここでは、以下の3つの観点から両試験の難易度を比較していきます。
1. 合格率の違い
| 試験年度 | 資格名 | 合格率 |
| 2024年 | 宅建士 | 18.6% |
| 2024年 | 賃貸不動産経営管理士 | 24.1% |
一見、賃貸不動産経営管理士の方が簡単に見えるかもしれませんが注意が必要です。宅建は長年にわたって難関国家資格として知られており、合格率は15〜17%前後を推移。一方、賃貸不動産経営管理士は国家資格化されたのが2021年からで、現在は難易度が年々上昇傾向にあります。
2. 合格ライン(基準点)の比較
| 試験年度 | 資格名 | 合格点(50点満点中) |
| 2024年 | 宅建士 | 37点(74%) |
| 2024年 | 賃貸不動産経営管理士 | 35点(70%) |
合格点で見ても宅建の方が高く、求められる正答率も上です。これは出題内容の深さ・厳密さが関係しており、宅建士は「受からせすぎない」ような問題構成になっていると考えられます。
3. 受験者数の比較
| 試験年度 | 資格名 | 受験者数 |
| 2024年 | 宅建士 | 約24万人 |
| 2024年 | 賃貸不動産経営管理士 | 約3万人 |
宅建士は毎年20万人以上が受験する超人気資格である一方、賃貸不動産経営管理士は国家資格化に伴って受験者が急増している段階。今後さらに競争が激化する可能性があります。
以上のようなデータから明らかなように、難易度という観点では宅建士が上です。そのため、まずは難易度の高い宅建士に集中し、基礎をしっかり固めた上で、賃貸不動産経営管理士に進むのが王道ルートと言えるでしょう。
チェックポイント
- 合格率:宅建の方が明らかに低い
- 合格ライン:宅建はより高得点が求められる
- 受験者数:宅建の方が圧倒的に多く、競争率も高い
ダブルライセンスは魅力的!だけど“順番”がすべて

不動産業界で注目されている「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」。両方を持っていれば大きな武器になりますが、いきなりダブル受験を狙うのは非効率でリスクが高いのも事実です。
カギになるのは 資格を取る“順番”。まず宅建士から挑戦することが、最短ルートでキャリアアップを実現する方法です。
まずは宅建士を取得すべき3つの理由
もし今あなたがキャリアの方向性に迷っているなら、最初に狙うべきは「宅建士」です。その理由は大きく3つあります。
- ①就職・転職に圧倒的に有利
- 宅建士は不動産業界で最も需要が高い資格です。求人票を見ても「宅建士歓迎」「資格手当あり」といった記載は圧倒的に多く、キャリアの安定につながります。
👉 宅建士が転職や昇進でどれほど有利になるのか?【宅建士の資格は転職・昇進に役立つ?実際の求人を調査】を詳しく解説。
- ②知識を賃貸管理士に流用できる
- 宅建で学ぶ民法や宅建業法の知識は、そのまま賃貸不動産経営管理士試験にも役立ちます。宅建を先に学んでおけば、次の試験で大きなアドバンテージになります。
- ③活躍のフィールドが広い
- 賃貸管理士が「賃貸管理」に特化しているのに対し、宅建士は賃貸・売買の両方に対応可能。将来、売買仲介や投資用不動産に関心を持った場合も、柔軟にキャリアを広げられます。
- つまり、宅建士を取ることは「業界での信用を得る」+「次の資格に活かせる」+「キャリアの選択肢を広げる」という“三拍子そろった一手”になるわけです。

不動産管理会社で働く私の立場から見ても、資格の恩恵を最大に感じるのはやっぱり宅建です。
1年目:宅建士に集中 → 2年目:賃貸管理士に挑戦
宅建士を先に取得するメリットが分かったところで、次は学習の進め方です。ポイントは「同時に狙わず、順番を分ける」こと。資格取得は「早く・多く」ではなく、「確実に・着実に」が成功のカギです。現実的で無理のないスケジュールは以下のとおりです。
1年目:宅建士に全集中
- 法律系科目をしっかり習得
- 民法などは賃貸管理士にも流用可
- 宅建業従業者なら講習を受けて5問免除を活用
2年目:賃貸不動産経営管理士にシフト
- 宅建で得た知識+設備・建物管理などの知識を追加
- 賃貸不動産経営管理士講習を受けて5問免除を活用
この順番なら「宅建で基礎を固める → 賃貸管理士で仕上げる」という理想的なステップアップが可能です。

できれば両方とも「5点免除者」として受験したいですね♪
キャリアアップを狙うなら順序がカギ
不動産業界では「宅建士+賃貸管理士」のダブルライセンスは大きな武器になります。とくに以下のようなシーンでは役立ちます。
- 賃貸管理会社への転職や昇進
- 法人化や独立開業時
- 信頼性のある営業担当者としての評価UP
ですが、この効果を最大化するには、順番が重要です。宅建を後回しにしてしまうと、逆に損をすることもあるので注意しましょう。
👉 2つの資格を比較して、転職に有利なのはどちらか?詳しくは【宅建士と賃貸不動産経営管理士、どちらが転職に有利?】をご覧ください。
焦らず着実に、確実にキャリアアップを!

「どうせならまとめて…」という気持ちは分かりますが、資格取得は“戦略”がものを言います。まずは宅建に全力投球してから、次のステップに進みましょう。
- ダブル受験は非効率でリスクが高い
- まずは宅建士に集中するのが最短ルート
- 宅建合格後に賃貸不動産経営管理士へ進めば、効率よくWライセンスを狙える
特に、社会人や子育て中の方は時間が限られています。独学で両方同時に目指すよりも、まずは通信講座を利用して「宅建士合格」を確実に狙うのがベストな選択肢でしょう。

宅建に合格した後なら、賃貸不動産経営管理士は独学で挑戦しても良いかもしれませんね♪
宅建士の通信講座を選ぶポイントは以下のとおりです。
- 合格率が高い講座(実績があるか確認)
- スキマ時間で学べる動画学習型
- 過去問・模試が豊富で添削や質問サポートあり
👉 独学に限界を感じた私が比較したおすすめの講座はこちら【8社を徹底比較!宅建おすすめ通信講座3選】
資格取得は「一気に取る」より「一歩ずつ積み重ねる」方が、結果的に早くゴールにたどり着けます。特に宅建士のように難易度が高い資格は、自分に合った学習スタイルを見つけることが何よりの近道です。
「独学で頑張るのもいいど、他の選択肢も見てみようかな」と、思ったときは一度学習方法を検討してみましょう♪