- 「転職で資格を取りたいけど、どっちの資格を取れば後悔しない?」
- 「家庭や育児と両立しながら、手堅く再就職できる道が知りたい」
- 「学生のうちに取ると一番役立つ資格ってどれ?」
そんな疑問や不安を抱えていませんか?
人は選択肢が多すぎると、行動できなくなってしまうものです。しかも、自分に合った道を選べているかどうか不安になると、前に進むこともできません。
だからこそ、まずは情報を整理して「自分に合った選択肢」を知ることが大切です。まず、結論からお伝えすると、転職を目的とするなら圧倒的に有利なのは宅建士です。
その理由は、宅建士の方が資格の知名度が高く、求人数も圧倒的に多く、手当や昇進に直結しやすいため、短期的にも長期的にも転職市場で有利に働くからです。
この記事では、宅建士と賃貸不動産経営管理士の違いを徹底比較し、実際の求人情報や資格ごとの活かし方、私の体験も交えながら「どちらがあなたに合っているのか?」を明確にしていきます。

将来の自分に合った選択をしていきましょう。
宅建士と賃貸不動産経営管理士の違いとは?

宅建士(宅地建物取引士)とは?
宅建士は、不動産売買や賃貸の契約時における重要事項説明や契約書の記名押印を担当する国家資格者です。宅地建物取引業者(いわゆる不動産会社)には、一定数の宅建士を配置することが法律で義務付けられているため、極めて需要が高い資格です。
- 活躍の場:売買仲介、賃貸仲介、不動産開発、投資不動産、管理会社など多岐にわたる
- 受験資格:なし(誰でも受験可能)
- 試験形式:50問(四肢択一)
- 合格率:約15〜18%前後
- 資格手当:月1万〜3万円程度が一般的
賃貸不動産経営管理士とは?
一方、賃貸不動産経営管理士は、賃貸物件の管理実務に特化した資格で、2021年に国家資格化された比較的新しい資格です。入居者対応や設備の管理、原状回復トラブルの調整など、現場業務での専門性が評価されつつあります。
- 活躍の場:賃貸管理会社、PM会社、オーナー代行業など
- 試験形式:50問(マークシート方式)
- 合格率:約30%前後
- 資格手当:月5,000円〜1万円程度
転職市場での評価:5つの視点で比較

① 求人数の多さ【宅建士に軍配】
転職サイトで「宅建士」「賃貸不動産経営管理士」と検索した場合、ヒット件数には大きな差があります。宅建士は1万件以上の求人に対し、賃貸不動産経営管理士は数千件程度にとどまるのが現状です。

企業からの需要が多い=採用されやすい、というのは転職活動において非常に大きなアドバンテージです。
② 資格の汎用性【宅建士が圧倒的】
宅建士は、売買・賃貸仲介・投資・不動産開発・不動産事務など、あらゆる職種で活かせる“万能資格”です。一方で賃貸不動産経営管理士は、賃貸管理業に特化しているため、職種が限定される傾向にあります。

たとえば、不動産業界の中で営業職に挑戦したい、開発部門に行きたいといったキャリアの選択肢を広げたいなら、宅建士の方が間違いなく有利です。
③ 年収・待遇【宅建士がリード】
宅建士資格には、資格手当がつく企業が多く、月1〜3万円の支給があるケースも珍しくありません。年間で見れば数十万円の収入アップに直結します。
一方、賃貸不動産経営管理士にも手当はありますが、金額は控えめで、あくまでプラスαという位置づけです。

宅建士資格は昇進や正社員登用の条件になっている企業もあるため、キャリアアップの観点からも有利です。
④ 試験の難易度【賃貸不動産経営管理士の方がやや簡単】
- 宅建士の合格率は約15〜18%で、出題範囲も広く、民法や宅建業法、税金、建築関連まで網羅。
- 賃管士は合格率30%前後で、宅建よりは合格しやすいとされますが、近年は難化傾向。
“先に取りやすい資格”として賃貸不動産経営管理士を目指す方もいますが、それを活かせる職場は限られるため、「取ったけど転職に活かせない」と感じるケースもあるようです。
⑤ ダブル資格の価値【非常に高い】
実は、両方持っていることで市場価値がグッと上がります。宅建士として契約を担当し、賃貸不動産経営管理士として建物管理や入居者対応の知識もある人材は、企業側にとって極めて重宝される存在です。

宅建士の方が転職市場で有利だけど、ダブルライセンスはもっと有利!
宅建士がおすすめな人の特徴とは?

1.「資格を武器にして、転職市場で一歩リードしたい」人
転職活動では、「何ができるか」が問われます。未経験OKの求人であっても、宅建士を持っているだけで書類選考の通過率が格段に上がるのはご存じですか?
実際に、転職サイトで「宅建士」と検索すると、求人数は常に1万件以上。多くの企業が「資格手当」「資格保有者歓迎」と明記しており、資格がそのまま“採用理由”になることも少なくありません。

一定数の宅建士を配置することが法律で義務付けられているため、資格を持っているだけで貴重な存在!
2. 「営業職で稼ぎたい」「成果を出して評価されたい」人
宅建士は、不動産売買や仲介業において“契約に直接関われる唯一の資格”。契約書に署名・押印できる宅建士がいなければ、売買契約そのものが成立しません。
つまり、宅建士=企業にとって絶対に必要な存在。だからこそ、インセンティブが高く、昇進や役職も優遇されやすいのです。
たとえば、私が勤める会社では
- 年収460万円 → 宅建取得後 → 年収610万円へ昇給
- 一般社員 → 宅建取得後 → 営業リーダー・店長へ昇格
こんな現実が、実際に多くの企業で起きています。
3. 「安定した仕事・待遇を得たい」人
宅建士を保有していると、以下のような待遇がついてきます。
- 資格手当:月1万~3万円(年間で12~36万円)
- 正社員登用や昇格の条件として評価される
- 不動産以外の業界(建築・金融・保険)にも応用できる
特に子育てが落ち着いたタイミングで再就職を考える主婦層からは、「宅建士を取ったら、年齢の壁を越えて正社員採用された」という声も多く聞かれます。

現に私が勤めている会社でも、再就職で活躍している方たちがたくさんいます。
4. 「不動産業界でキャリアを広げたい」人
宅建士を取得すると、不動産業界で働くうえで“転職の自由度”が圧倒的に上がります。なぜなら、売買仲介 → 賃貸仲介 → 管理会社 → デベロッパー など業態や職種をまたいでも、宅建士の知識はすべての現場で通用するからです。
逆に、賃貸不動産経営管理士は“賃貸管理業”に特化しており、キャリアの幅は限定的。“キャリアを広げたい”と考えるなら、まず宅建士が土台になるという事を覚えておきましょう。
5. 「将来的に独立・副業も考えている」人
- 不動産仲介業を開業(宅建士は1名以上必須)
- 不動産投資家として物件購入時にリスクを見抜く
- 副業で不動産コンサルタントやセミナー講師に
といったように、宅建士の資格を活かして“会社に依存しない働き方”を実現している人も多くいます。
宅建士は「不動産業を始めるためのパスポート」とも言える存在。長期的に見れば、可能性が広がる国家資格です。

現に私が勤めている会社でも、ある程度人脈や経験を積んだ後に独立する人が多いです。
賃貸不動産経営管理士がおすすめな人の特徴とは?

1. 「宅建士よりも、実務寄りの知識を身につけたい」人
「宅建士は法律よりだけど、実際の現場で使える知識がほしい」そんな方には、賃貸不動産経営管理士が最適です。
この資格では、以下のようなリアルな現場の問題に対応する知識が学べます。
- 設備トラブル対応(エアコンが壊れた、排水が詰まった…)
- 原状回復の範囲はどこまでか?(敷金トラブル)
- 高齢者入居やペット可物件の管理上の注意点
- サブリース契約のリスクと適切な運用方法

法律知識+実務スキルが求められる不動産業界において、“管理のプロ”としての評価が得られる資格です。
2. 「管理会社やPM(プロパティマネジメント)職に就きたい」人
宅建士が“契約”のプロなら、賃貸不動産経営管理士は“運営とトラブル解決”のプロ。
近年はサブリース問題や孤独死対応、高齢者入居増加などを背景に、賃貸管理業界は専門性を持った人材を強く求めています。
実際に、管理会社の求人の中には以下のような文言が見られます。
- 「管理士保有者は優遇します」
- 「宅建+管理士の方は即戦力として採用」
- 「資格手当 月8,000円(宅建士とのW資格で最大3万円)」

まだ取得者が少ない資格だからこそ、差別化の武器になります。
3. 「宅建士をすでに持っていて、ステップアップしたい」人
宅建士をすでに取得済みなら、次に目指すべきは賃貸不動産経営管理士です。なぜなら、宅建士ではカバーできない“運用面”の知識を補完できるから。
両方の資格を持つことで、以下のようなシーンで活躍の幅が広がります。
- オーナーから「修繕費って借主が負担するんだっけ?」と聞かれても即答できる。
- 入居者からの設備トラブルに対して、適切な対応判断ができる。
- 社内で「法律と実務、両方わかってる人」として頼られる

“現場をわかってる宅建士”は、企業から見れば非常に魅力的な人材です。
4. 「子育てや介護と両立しながら働きたい」人
賃貸不動産経営管理士の業務は、ルーティンかつ安定した働き方が可能な職場が多いのが特徴です。
- 内勤中心の事務職(シフト制、土日休みあり)
- コールセンターや入居者対応サポート
- 物件点検や簡易的な巡回などの軽作業
実際に、子育てが落ち着いた主婦の再就職先として、賃貸管理会社での勤務が人気です。宅建士ほどプレッシャーのかかる契約業務が少なく、柔軟な働き方を実現しやすいのが魅力です。

私が勤める会社でも、サポート役で多くの主婦層の方が活躍しています。
5. 「将来、賃貸経営や管理業務を自分でもやってみたい」人
不動産投資や相続物件の管理など、“自分自身がオーナー側になる将来”を考えているなら、この資格の知識が大いに役立ちます。
- 賃貸経営における収支バランスの考え方
- クレームや滞納への適切な対処法
- 原状回復工事や設備交換の見積もり判断力
不動産の「持ち方」「運用の仕方」まで見据えたい人にとって、実務知識を得られる管理士資格は非常に実践的です。

私の会社でも実務経験を活かして投資物件を所有している社員が副業でオーナー業をしています。
賃貸不動産経営管理士は派手さはなくても、確かな実務力が身に付けることができます。宅建士を取得済みの方、または実務志向の方にとって、賃管士は次のステップとして非常に魅力的な選択肢です。
求人実例で見る「求められる資格」
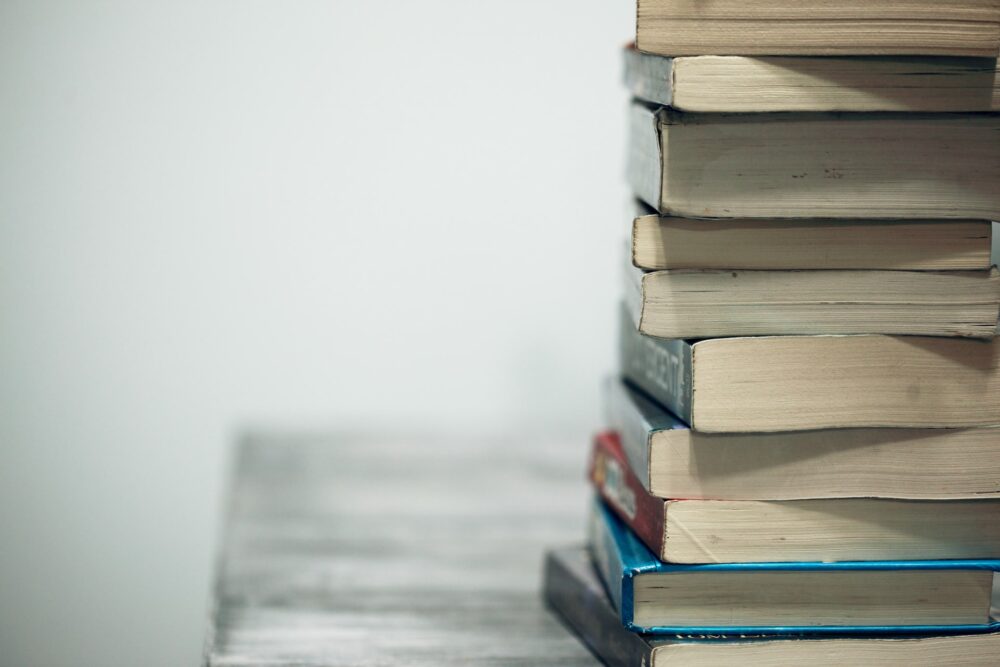
資格は取得して終わりではなく、“現場でどう評価されているか”が大切です。ここでは、全国各地(都市部・地方含む)の求人情報や転職サイトの統計データをもとに、宅建士と賃貸不動産経営管理士の「実際のニーズ」を比較していきます。
宅建士の求人例【全国平均】
求人数・資格必須率
- 全国の公開求人数(リクナビNEXT・doda・ハローワーク含む):約10,000〜13,000件/月
- 宅建士必須の求人割合:約55〜65%(とくに売買仲介・不動産投資・開発系で必須)
▶︎ 平均年収・待遇
- 正社員年収の全国平均:約370万円〜520万円(地方は300万円台前半から)
- 資格手当平均:月10,000〜25,000円(全国平均:約15,000円/月)
- 昇進や役職の条件に含まれる割合:中堅以上の企業で約40%
▶︎ 職種例
- 不動産営業(賃貸・売買)
- 不動産事務(契約書作成・法務確認)
- 不動産管理(収益物件対応含む)
- 金融系(住宅ローン審査/不動産担保評価)

全国どの地域でも安定的にニーズがある汎用資格。地元で就職・転職したい人にもおすすめ。
管理士の求人例【全国平均】
▶︎ 求人数・資格要件
- 全国の公開求人数:約1,200〜1,800件/月(管理会社やPM業務中心)
- 資格必須の求人割合:10〜15%程度(ほとんどが「優遇・歓迎」扱い)
▶︎ 平均年収・待遇
- 正社員年収の全国平均:約320万円〜420万円
- 資格手当平均:月3,000〜8,000円(全国平均:約5,500円/月)
- 地方の中小企業では「自己学習評価」の一環として見られるケースも
▶︎ 職種例
- 賃貸管理業務(入居者対応・更新契約・原状回復)
- PM担当(オーナー対応・収支レポート作成)
- 不動産事務(少人数の不動産会社で兼任業務)
- コールセンター・サポートスタッフ(物件問合せ対応)

実務に直結する資格だが、宅建士よりも求人数は限られているのが現実。
独学 vs 通信講座:どちらが合格への近道?

「できればお金をかけずに、自分の力で受かりたい」「通信講座って本当に効果あるの?」そう考えていたのは、私自身です。
実は私、宅建試験に独学で4回落ちました。5回目でようやく合格したものの、正直、「もっと早く通信講座を使っていれば…」と今でも後悔しています。
独学は想像以上に難しい
独学のメリットは、費用が抑えられること。でもその代わり、以下のような“見えない壁”にぶつかります。
- どこが重要か分からず、テキストを何周しても不安が残る
- 法改正や出題傾向の変化に気づかず、時代遅れの勉強を続ける
- 「これで大丈夫なのかな…」という不安から、行動が止まる
- 模試を受けても結果が読めず、合格点まで届かない
実際、私は4回目の受験時に「自分のやり方には限界がある」と感じました。“やってるつもり”でも、合格ラインに届かない。そんな経験を何度も味わいました。

過去問は完璧なのになぜか合格ができない。そんな失敗を何年も繰り返していました。
通信講座を使ったら、他資格は一発合格できた
皮肉なことに、他の不動産資格(管理業務主任者やマンション管理士)では、通信講座を活用してスムーズに合格できました。
- 出題傾向を熟知した講師が“本当に出るところ”を教えてくれる
- 最新の法改正・統計データが教材に即反映されている
- 自分の理解が浅い部分を、動画や添削で“可視化”してくれる
- モチベーションを支えてくれる進捗管理やコミュニティがある

「学習は自己責任。でも、効率化はプロに任せてもいい」そう思えるようになった時、勉強がラクになり、結果が出るのも早くなりました。
合格までの“時間と機会”をどう考えるか?
- 独学で3年かけて合格 or 通信講座で1年で合格
- 毎年1回のチャンスを、今年で終わらせるか、また来年も受けるか
試験に失敗してしまうと、「時間の損失」と「自信喪失」が付きまといます。特に社会人や主婦の方にとっては、1年1年が本当に貴重です。
「独学で挑戦したい」という気持ちはとても素晴らしい。でも、もし過去の私と同じように“やってるのに受からない”状態なら、通信講座という選択肢を、“妥協”ではなく“戦略”として受け入れてほしいです。
私は宅建に5年かかりました。もしあのとき、自己投資をして通信講座を選んでいたら、今頃はもっと早く資格を活かしてキャリアアップできていたと思います。「もったいないのは、講座代じゃなく、遠回りした時間でした。」だからこそ今、迷っているあなたには“確実性を高める手段”としての通信講座という選択肢を、ぜひ一度だけでも、真剣に検討してほしいと思っています。

自分の将来や人生設計を考えて、いつまでに資格を取得するべきなのかをもう一度よく考えてみましょう。
迷ったら宅建士から挑戦するべき
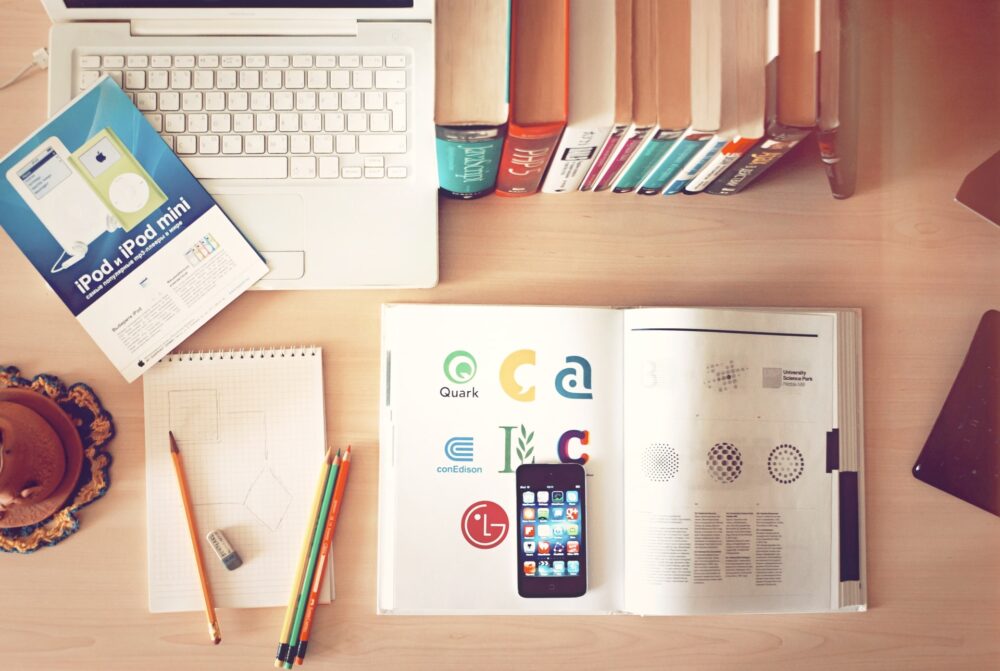
宅建士と賃貸不動産経営管理士は、どちらも不動産業界で活躍するための有力資格ですが、転職市場でのインパクトを考えると、まず取得すべきは間違いなく「宅建士」です。
- 求人数が圧倒的に多く、全国どこでもニーズがある
- 契約に関わる“唯一の国家資格”として企業から重宝される
- 職種も働き方も選びやすく、将来の可能性が広がる
- 資格手当や昇進に直結し、年収アップにもつながる
- 取得後に「賃貸不動産経営管理士」などの専門資格を追加できる柔軟性がある

つまり、宅建士は「キャリアの土台」として最も強力な資格ということです。
私自身、宅建士を取得してから明らかに世界が変わりました。資格を持っているだけで、顧客や社内からの信頼も高まり、「一目置かれる存在」になったのを実感しています。
そして何より、「この資格がある自分なら大丈夫」と思える自信がつきました。
今、あなたの中に少しでも「何かを変えたい」「動き出したい」「このままでは終わりたくない」という気持ちがあるならその第一歩として、宅建士の勉強を始めてみてください。
大丈夫です。過去に4回も不合格だった私でも、5回目で合格できました。本気になれば、どんなスタートでも変えられます。
まずは宅建士を取得して、その後に賃貸不動産経営管理士を取得する。これが最も堅実で失敗の少ないルートだと私は思います。