- 宅建って、実際の難易度ってどうなの?
- 子育てや仕事をしながらでも、合格できる?
- 独学で受かる人もいるらしいけど、本当?
- 何度も落ちている人を見ると、自分にできるか不安…
宅建士(宅地建物取引士)は、法律系資格の中では比較的「身近な国家資格」として知られています。宅建業法により、不動産取引には必ず宅建士の設置が必要とされているため、業界の需要は常に高く、転職・就職でも有利に働くことが多いです。
しかし、その一方で合格率は毎年15〜18%前後と低く、「手軽に取れる資格」というイメージは少し誤解を含んでいるのも事実です。
この記事では、宅建試験の合格率データや難易度、試験傾向、そして社会人・主婦・学生が直面するリアルな難しさについて詳しく解説します。
宅建士試験の合格率と受験者数の推移

過去10年の合格率データをチェック
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |
| 平成27年 (2015年) | 243,199名 | 194,926名 | 30,028名 | 15.40% | 31点 |
| 平成28年 (2016年) | 245,742名 | 198,463名 | 30,589名 | 15.41% | 35点 |
| 平成29年 (2017年) | 258,511名 | 209,354名 | 32,644名 | 15.59% | 35点 |
| 平成30年 (2018年) | 265,444名 | 213,993名 | 33,360名 | 15.59% | 37点 |
| 令和元年 (2019年) | 276,019名 | 220,797名 | 37,481名 | 16.98% | 35点 |
| 令和2年 (2020年) | 259,284名 | 204,247名 | 34,337名 | 16.81% | 36点・38点 |
| 令和3年 (2021年) | 296,518名 | 234,714名 | 41,471名 | 17.67% | 34点・34点 |
| 令和4年 (2022年) | 283,856名 | 226,048名 | 38,525名 | 17.04% | 36点 |
| 令和5年 (2023年) | 289,096名 | 233,276名 | 40,025名 | 17.16% | 36点 |
| 令和6年 (2024年) | 301,336名 | 241,436名 | 44,992名 | 18.64% | 37点 |
ここ10年間、合格率はおおよそ15〜18%で安定していますが宅建試験は“相対評価”であるため、得点が50点満点中35点でも合格する年もあれば、37点必要な年もあります。過去のデータから見ると、合格ラインは±36点で38点を目標に勉強すれば安心だといえるでしょう。
宅建士試験はわずか1点のミスで不合格になってしまうシビアな試験です。まずは合格ラインである±36点を超えるということはもちろん大事なことですが、本番ではいかに「取りこぼしをしないか」が重要になってくる試験です。

難しい問題を解けることよりも、他受験者が得点できる問題は必ず得点する力が合格のカギになってきます。
宅建士の難易度は?他の資格と比較してみよう

| 資格名 | 合格率 | 勉強時間 | 難易度(体感) |
| 司法書士 | 約3~5 % | 3,000時間 | 超難関 |
| 土地家屋調査士 | 約9〜11 % | 1,000時間 | 難関 |
| マンション管理士 | 約8〜12 % | 500~700時間 | 難関 |
| 宅建士 | 約15〜18 % | 300~400時間 | 中〜上級 |
| 管理業務主任者 | 約20〜23 % | 300時間 | 中〜上級 |
| 賃貸不動産経営管理士 | 約24.1 % | 100時間 | 中程度 |
この表を見ると、宅建士の合格率は15%~18%となっています。マンション管理士、宅建士、管理業務主任者、賃貸経営不動産管理士の4資格を取得した私の体感では宅建試験は中~上級の難易度だと感じています。
また、宅建士は「独学で取れる国家資格」とも言われており毎年多くの人が独学で挑戦していますが、その大多数は受験経験者や法律・不動産関連の知識を持つ人です。
まったくの初心者、特に法律に触れたことがない社会人や主婦の方にとっては、テキストの文章が難解に感じることも多く、“初学者向け”とは少々言い難いのが実情です。
もちろん独学で合格することは十分に可能です。ただ、テキストをこなすだけでは合格ができない試験だということを理解したうえで挑戦しましょう。
特に社会人が感じる宅建の難しさとは?
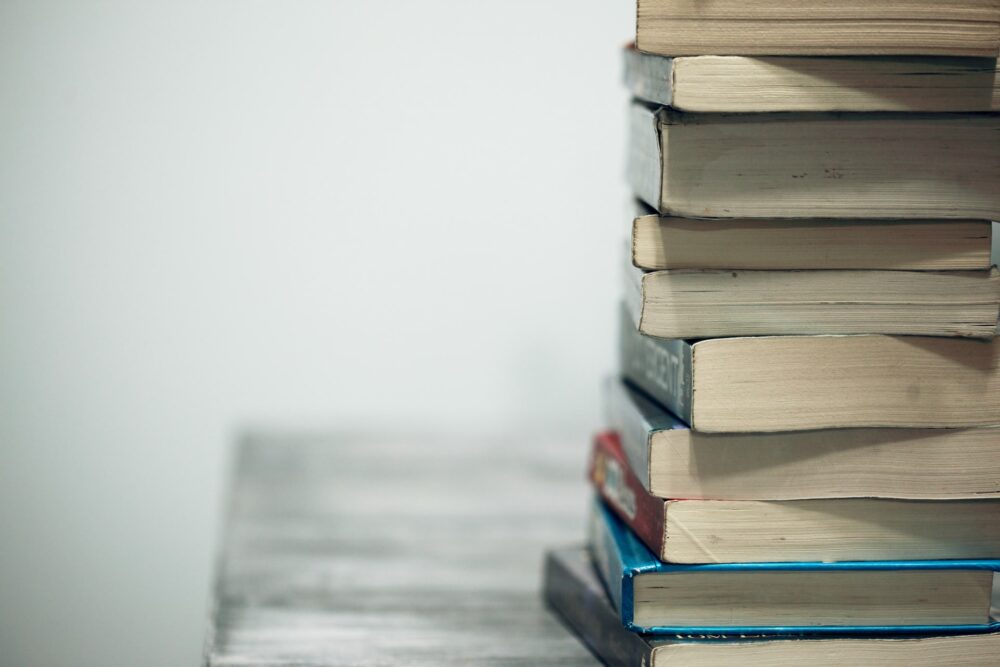
1. 時間が圧倒的に足りない
- 毎日の仕事に追われ、勉強の時間が取れない
- 「朝活しよう」と決めても、眠気に勝てない
- 休日は家事・育児・人付き合いであっという間に終わる
社会人が宅建に挑戦するうえで、最大のハードルは「時間の確保」です。私も最初は「通勤時間や夜の1〜2時間を使えば、何とかなるだろう」と軽く考えていましたが、実際は全然うまくいきませんでした。

「やる気はあるのに、時間がない」このもどかしさは、経験した人にしかわかりません。
2. ひとりで学習を進める孤独感
- 誰にも相談できない
- 現時点での自分の実力がわからない
- 今の勉強法が正しいのか不安になる
- 周囲の声を聞いて、自分は置いていかれているような気がする

一人で机に向かう時間が長くなるほど、不安や焦りも積み重なっていきます。
3. 継続するのがとにかく難しい
宅建の勉強は、長い戦いです。「やる気があるうちに一気に!」なんて思っていても、現実はなかなか続きません。特に社会人は、勉強仲間もいなければ、進捗を確認してくれる人もいない。それが地味にきついんです。
私が感じたモチベーションが落ちるときは以下のようなときでした。
- 疲れて帰ってきて、勉強する気力が残っていない
- 休日、頑張って勉強したのに全然頭に入ってなかったとき
- 同僚が趣味や旅行を楽しんでいるSNS投稿を見たとき
- 過去問を解いても全然点数が伸びなかったとき
- 「あと○ヶ月か…間に合わないかも」と焦ったとき
社会人が一人で学習を進めると、こうした孤独感や不安に悩まされやすくなります。はっきり言うと独学で継続できるのは、強い目的意識と計画性がある人に限られるのが現実です。

最初はあんなに意欲的だったのに、気づけば勉強から遠ざかっていた。そんな経験ありませんか?
合格に必要な勉強時間とスケジュール設計

宅建士の試験に合格するために必要とされる学習時間は、おおよそ300〜400時間が目安とされています。これは、法律知識がゼロの初心者でも合格を狙えるラインです。ただし大事なのは、「時間の長さ」よりも「使い方」です。
勉強時間と目安のスケジュール
| 1日あたりの勉強時間 | 必要な期間 |
| 1時間 | 約10ヶ月 |
| 2時間 | 約5〜6ヶ月 |
| 3時間 | 約3〜4ヶ月 |
例えば、1日2時間コツコツ勉強できる人なら、半年ほどで合格ラインに届く可能性があります。でも、それは「やるべきことを、やるべき順番で、効率よくこなせた場合」に限ります。
勉強時間=成果 ではない
次のような勉強法では、どれだけ時間をかけても成果が出にくいので要注意です。
- テキストを最初から全部読もうとして、挫折してしまう
- 過去問を“解くこと”が目的になってしまい、理解が伴わない
- 難しい内容に詰まって長時間止まり、全体のペースが崩れる
- 毎回復習がバラバラで、知識が定着しない
私自身も独学のときは、「平日1時間、休日は3時間!」と意気込んでスケジュールを立てたのですが、現実には…
- 疲れて帰ってきて、30分も集中できない日が続く
- 土日は家の用事や付き合いで、まとまった勉強ができない
- スケジュールが崩れてやる気を失い、そのまま1週間放置
ということを繰り返していました。

結果、学習時間は300時間を超えていたのに、全く点数が伸びないという状況に。
大切なのは「毎日の習慣化」と「無理のない計画」
宅建試験の勉強では以下のような工夫があると、忙しい人でも継続しやすくなります。
- 朝の通勤時間や昼休みに10〜15分ずつ動画や音声学習、他復習など
- スマホでサクッと解ける過去問アプリを活用
- 毎週の目標を「小さな単位」で設定する(例:1日5ページだけ)
- 「時間を確保する」よりも「今の生活に学習をどう組み込むか」を意識する
時間がないからこそ、やるべきことを最小限に絞り、効果の高い順に取り組むことが合格への近道です。逆に、情報が多すぎたり、自己流で迷子になってしまうと、倍の時間をかけても届かない可能性すらあります。

自分にとっての「最短ルート」を選ぶことが、合格の第一歩です。
宅建試験の出題傾向と合格戦略
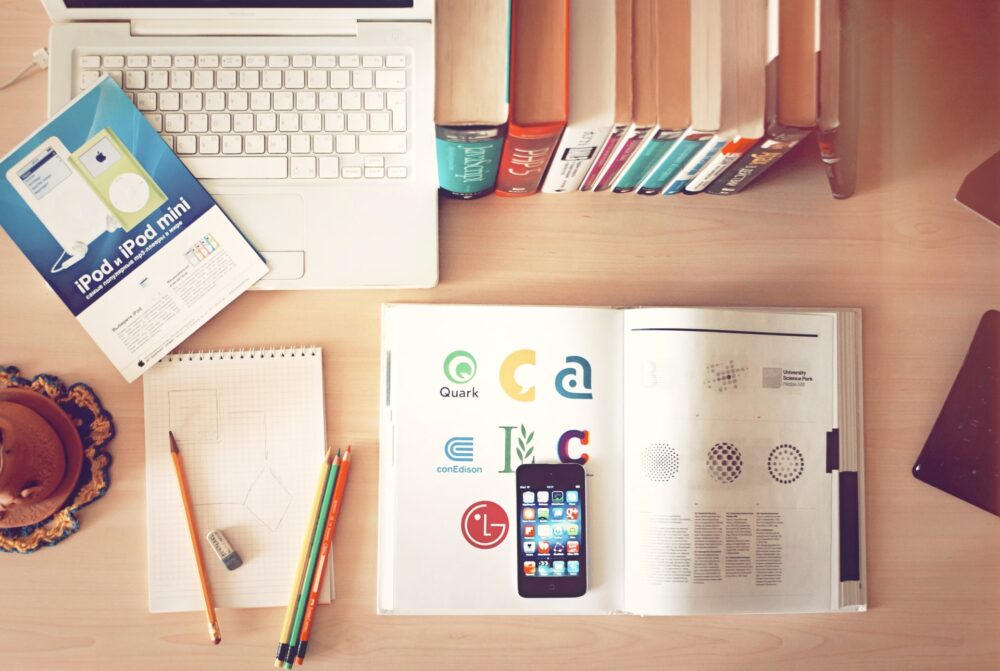
宅建士試験は、毎年20万人以上が受験する超人気資格です。しかし、そのうち合格できるのは約15〜18%前後。数字にすると、およそ6〜7人に1人しか合格できない計算になります。
「意外と合格率低いな…」と感じた方もいるかもしれません。でも、ここで注意していただきたいのが、この試験は“絶対評価”ではなく“相対評価”**という点です。
つまり、「50点満点中何点以上で合格」ではなく、受験者全体の上位約15%前後に入らなければ不合格という、非常にシビアな仕組みになっています。
昔と今では、合格戦略がまるで違う
■ 過去の宅建(〜2010年代前半)
- 問題が素直で、暗記で十分対応できた
- 過去問と“ほぼ同じ”選択肢が出ることも多かった
- 法改正も少なく、1度覚えれば通用する知識が多かった
■ 近年の宅建(2020年代)
- 2020年の民法改正以降、判例や細かい法解釈を問う問題が増加
- 出題文の長文化+複雑化(例:1問で2つ以上の知識を組み合わせて解答)
- 「どれが正しいか」ではなく「どれが最も適切か」といった選びにくい設問
- 毎年1〜2問は“完全な初見問題”(過去問の使い回し不可)
たとえば2023年度試験では、民法から【複数の債権者と債務者間の特約】という、専門書でも見かけるレベルの論点が出題され、正答率が10%以下という設問もありました。

民法の難問化はかなりつらい。
「過去問3回やれば受かる」は、もう通用しない
もちろん過去問は重要ですが、それだけでは不十分です。なぜなら近年の宅建試験は、次のような力を求めているからです。
- 単なる知識の暗記だけでなく、法律的思考力(条文の解釈)
- 初見テーマにも動じない読解力と判断力
- 細かな数字(床面積要件、罰則金額など)や時系列の記憶
- 最新の法改正や制度変更をキャッチする力
実際、2024年度の合格ラインは37点(50点満点で、前年よりも高く、過去10年で最も点数が必要だった年と並びました。

つまり、「ちょっとミスしただけで不合格になる」レベルの厳しさになってきているのです。
合格するための戦略は“計画”と“優先順位”
試験範囲が広い宅建士試験では、闇雲に全分野を均等に勉強しても、時間が足りなくなります。そのため、戦略的に「得点源」と「捨て問候補」を見極める必要があります。
出題割合の目安(50問中)
| 分野 | 問題数 | 合否への影響度 |
| 宅建業法 | 約20問 | 高(必須) |
| 法令上の制限 | 約8問 | 中 |
| 民法・権利関係 | 約14問 | 高(難化傾向) |
| 税・その他 | 約8問 | 低〜中 |
宅建業法は、最も配点が高く難易度も安定しているの落とせない分野です。この分野で得点できないとまず合格は厳しいと言えるでしょう。逆に、「統計問題」「税金の細かい制度」は捨て問候補と割り切る戦略も有効でしょう。

実際に私が合格できた時は宅建業法は全問正解でした。
難化する今だからこそ、“学習の質”がすべて
近年の傾向を見ると、以下のような声が多くなっています。
- 「過去問だけでは対応できない問題が増えている」
- 「独学では、出題意図や選択肢の引っかけ方に気づけなかった」
- 「全範囲を自分一人で整理するのが難しい」
このように、情報の整理・優先順位の判断・法改正への対応など、“ただ勉強する”だけでは太刀打ちできない要素が増えています。
だからこそ、「効率よく、的を絞って学べる環境」を用意できるかどうかが、合否を分けるポイントになります。
- 限られた時間で、何を、どこまで、どう学ぶか
- 今の学習方法で、36点以上を本番で取れる自信があるか
- 「間違ったやり方で数ヶ月を無駄にする」リスクを避けられているか
少しでも不安があるなら、学習の環境を整えることから始めてみるのも良いかもしれません。

“やる気”がある人ほど、正しい方法を選ぶことで合格に繋がりやすくなります。
独学と通信講座、どちらが現実的か?

体験談:独学で4回不合格
「独学でも宅建は合格できる」たしかに、それは事実です。ですが私は、その言葉を信じて4回連続で不合格になりました。
- 1回目:とにかく市販のテキストと過去問を回す。
- 2回目:とにかく市販のテキストと過去問を回す。
- 3回目:過去問をひたすら回す。過去問にでてくる問題は完璧。
- 4回目:過去問をひたすら回す。過去問にでてくる問題は完璧。
- 5回目:「これでダメならもう無理かも」と過去問をひたすら回して合格。
毎回、「今度こそ」と思って始めるのに、終わるころには「また1年、無駄にしてしまった…」という後悔だけが残り心が折れそうになりました。

よく諦めなかったな、、、と今でも思います。
独学でつまずきやすいポイント
- 勉強の進め方が自己流で、どこかで遠回りしている
- 「理解したつもり」で先に進んでしまい、応用問題でつまずく
- スケジュールやモチベーションが日々の生活に押し負ける
- つまずいたとき、相談できる相手がいない

時間も努力も注いだのに、結果に結びつかない瞬間はかなり精神的なダメージがありました。
当時の私は、「独学で受かった方がかっこいい」とさえ思っていました。でも、4度の不合格を経験して思うのは、結果を出すことの方がよっぽど大切だったということです。
合格するために必要なのは、「全部一人でやり切る力」ではなく、自分が続けられる環境と、正しい学び方を選ぶことだと今なら断言できます。
特に以下のような環境で勉強できるかを意識しましょう。
- 毎日の勉強ペースが決められている。
- 苦手な科目を補ってくれる補助ツールや解説がある。
- 法改正や出題傾向を“まとめて整理してくれる情報源”がある。
短期間で合格をしているほとんどの人は「自分に合った学び方」を早い段階で見つけています。それが独学なのか通信講座なのかは人それぞれです。
だけど、もし今のあなたが、独学で「少しでも不安がある」「このやり方で大丈夫かな」と思っているなら、一度立ち止まって、“より合格に近い方法”を見つけることが、大きな一歩になるかもしれません。

「一人でやる」ことにこだわる必要はまったくありません。
宅建試験は独学可能。でも“甘く見ない”ことが合格の鍵

宅建は独学でも合格できる資格です。でも、それは「時間と知識、そして継続力」がそろって初めて成立する話だと、私は4回の不合格を通して痛感しました。
特に今の宅建試験は、法改正や出題傾向の変化で、昔のように「過去問だけ」では通用しなくなっています。
- 合格率は15〜18%と低く、相対評価で競う厳しい試験
- 社会人・主婦にとっては「時間の壁」「理解の壁」「継続の壁」が大きい
- 独学で成功するには強い意志と時間管理能力が必須
- 通信講座の活用で、効率的かつ確実な合格が現実的に
また、宅建試験は、正しい方向に努力できるかどうかで結果が大きく変わります。だからこそ、「自分に合った学び方」を早めに見つけることが、最短ルートになります。
「独学で挫折したくない…」「確実に合格したい」そんなあなたには、短期間で効率的に合格を目指せる通信講座の活用がおすすめです。実際に合格者の多くが講座を利用して成功しています。

私のように独学で何年も足踏みしないようにしてほしいです。
✅ 確実に合格を目指す人はこちら → [宅建通信講座おすすめ比較ページ]