
- いつから勉強をするべき?
- 必要な勉強時間はどのくらい?
- 独学で合格は難しい?
宅建試験は、不動産取引に関する専門的な知識を問う国家試験です。そして、不動産業界だけではなく幅広い業界で活用ができるコスパの良い資格として非常に人気のある資格です。
この試験は、宅建業法、民法、法令上の制限など専門知識や法律の理解が必要でそれぞれの分野でバランスよく得点できるのかが合格のポイントになります。
想像以上に学習範囲が広いので、「勉強時間が足りずに不合格」という結果にならないように注意しましょう。そのためには余裕を持った学習計画を組み立てることがとても重要です。

私は勉強不足で何度も試験に落ちてしまいました。
この記事では、私が宅建試験に合格した経験から試験突破に必要な勉強時間と学習方法について解説します。
この記事を読めば「勉強時間が足りずに不合格になってしまった」と失敗することはありません。

仕事や育児で時間に余裕がない人ほど学習計画を組み立てましょう。
勉強時間の目安について
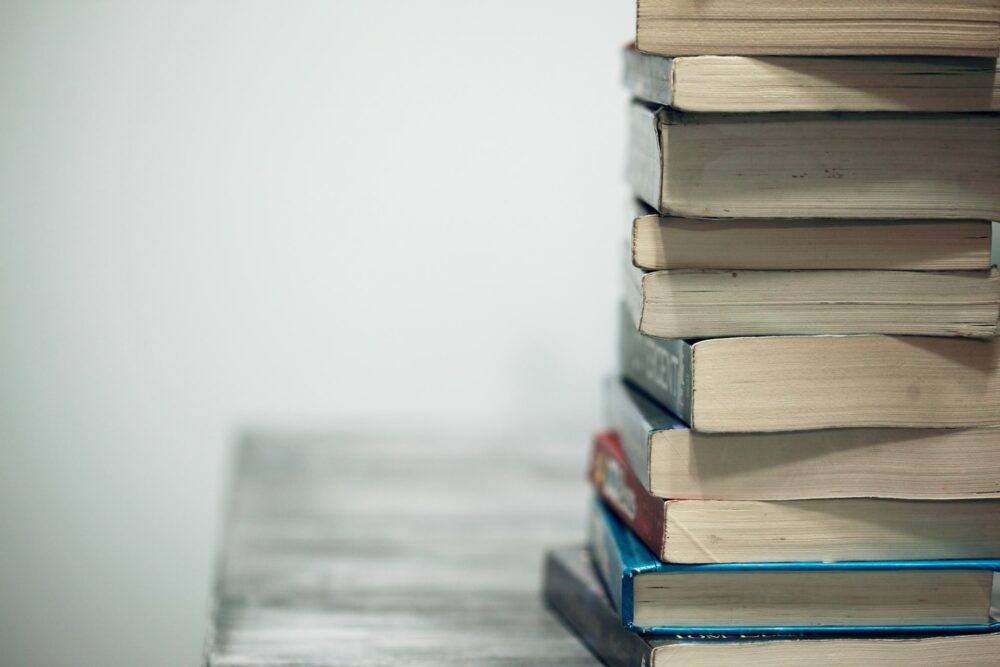
宅建試験に合格するためには、一般的に200~400時間程度の勉強時間が必要だと言われています。これは1日に確保できる勉強時間が2~3時間だとすれば3ヶ月~半年ほどかかる計算です。

もちろん、個人差はあります。
一般的には以下のような目安があります。
初心者の場合
- 総勉強時間:約600時間
- 1日の勉強時間:2~3時間
- 勉強期間:約8カ月
経験者の場合
- 総勉強時間:約300時間~400時間
- 1日の勉強時間:1~2時間
- 勉強期間:約4カ月
不動産経験のない初心者が独学で試験に挑戦する場合は、約600時間以上の勉強が必要になることは想定しておきましょう。
なぜなら、この試験は以下のような特徴があるからです。
- 専門用語が多い
- 法律の問題が広い
試験科目は、民法(権利関係)・法令上の制限・宅建業法、税、その他(免除科目)の4科目で構成されています。本試験は2時間の試験で出題範囲は基礎から応用まで幅広く、実務や法改正に対応した内容が含まれます。
宅建の試験科目
| 科目 | 出題数 |
| 民法(権利関係) | 約14問 |
| 法令上の制限 | 約8問 |
| 宅建業法 | 約20問 |
| 税・その他 | 約3問 |
| 免除科目 | 5問 |
宅建試験は多くの不動産知識を要求される試験なので、初心者が短期間で合格することは非常に難しいで試験です。早めに勉強を始めて少しずつ知識を定着させることが最も効果的です。
一般的には、試験日の半年前から準備を始めることを推奨されていることが多いですが。もっと早い時期から勉強を開始すれば時間の確保が難しい人でも無理なく本試験までに基礎知識を身に付けることが可能になります。
無理をすることなく知識を定着させて合格を目指しましょう。

早めに勉強を始めることが何よりも大事!
基本の勉強方法は3つのステップ

管理業務主任者試験の基本の勉強方法は、以下の3つのステップで勉強することがおすすめです。
- テキスト学習
- 過去問
- 予想問題、模擬問題
①テキスト学習
宅建試験の勉強方法の第一歩は、テキスト学習です。テキストを読んで試験に必要な知識を教材から学習しましょう。
テキスト学習をすることで、以下の2つのメリットがあります。
- 試験範囲を網羅する
- 基礎力を身につける
テキストを読み込むことで、試験範囲を網羅し基礎力を身につけることができます。
宅建試験は、応用力も求められる試験ですが、応用力を発揮するためには基礎力が不可欠です。
まずはテキスト読んで基礎的な用語や概念を理解しましょう。
②過去問
宅建試験の勉強方法の第二歩は、過去問です。過去問とは、過去に実際に出題された問題のことです。
過去問を解くことで、以下の3つのメリットがあります。
- 出題傾向を把握する
- 応用力を鍛える
- 自分の弱点を見つける
過去問を解くことで、出題傾向を把握することができ応用力も鍛えることができます。
宅建試験は、実際の事例や状況に対応した回答が求められます。単に覚えた知識をそのまま覚えても合格はできません。
過去問を解くことで、自分の弱点を見つけることができます。自分の得意な科目や苦手な科目、得点力の高い分野や低い分野などを把握しましょう。
市販の一問一答のテキストは必要ない
独学で学習する時に、持ち運びに便利なので「一問一答」の問題集の購入を悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
試験当日の確認作業としては便利なアイテムではありますが、使い方次第ではデメリットになってしまうこともあります。
一問一答テキストのデメリットは以下の通りです
- 使用するテキストが増えてしまう
- 答えの正解、不正解だけで満足してしまう
- 解説が簡略化されていて不十分
- 暗記メインになってしまう
- 覚えた気になる
一問一答は理解が浅くなりがちです。できる限り本番に近い環境で問題を解く練習をすることが大切です。
どうしても、一問一答のテキストを活用したい場合は「確認用のツール」として使用するようにしましょう。

基礎固めの学習で一問一答は危険です。
③予想問題、模擬試験
模擬試験とは、実際の試験と同じような条件で問題に取り組むことです。
模擬試験を受けることで、以下の2つのメリットがあります。
- 時間配分や回答方法を身につける
- 自分の得点力や弱点を把握する
模擬試験を受けることで時間配分を身につけることができます。宅建試験は、2時間にわたって4科目の試験を受ける試験です。制限時間内に全ての問題に回答するためには、効率的な方法を習得する必要があります。
模擬試験を受けることで、自分の得点力や弱点を把握することができます。自分がどの科目や分野で得点できるかやどこで失点しがちかを知ることが大切です。模擬試験を受けることで、自分の得点力や弱点を客観的に評価することができます。
具体的な勉強スケジュール

宅建試験の勉強開始時期は、試験の半年以上前もしくは1年前から始めることをおすすめします。これは400時間以上の勉強を無理なくこなすために必要な期間だからです。

勉強時間の確保が難しい人こそ、早くから勉強を開始するべきです。
たとえば、400時間を勉強する場合、以下のようなスケジュールを考えてみましょう。
- 試験1年前から学習する場合
- 1ヶ月に約33時間、週に約8時間、1日平均で1.1時間程度
- 試験9ヶ月前から学習する場合
- 1ヶ月に約45時間、週に約11時間、1日平均で1.5時間程度
- 試験6ヶ月前から学習する場合
- 1ヶ月に約63時間、週に約16時間、1日平均で2.1時間程度
- 試験3ヶ月前から学習する場合
- 1ヶ月に約129時間、週に約32時間、1日平均で4.3時間程度
このように、学習開始時期が遅れるほど必要な勉強時間が増えてしまいます。

特に3ヶ月前から始める場合は、非常に厳しいスケジュールになりますね。
もちろん、これらはあくまで目安です。自分の学習スタイルやペースに合わせて調整することが一番大切です。しかし初心者の独学で挑戦する場合は、なるべく試験の1年前から勉強を始めましょう。
おすすめの勉強スケジュールは以下のとおりです。
- 【1~7月】テキストの読み込みと過去問の周回
- 【8月~9月】苦手分野の克服
- 【10月~】総仕上げ
- 【直前期】予想問題で知識の積み上げ
宅建試験の試験日は10月の第3日曜日です。3ヶ月で400時間以上の時間の確保ができそうであれば7~8月頃に勉強を開始しても間に合います。半年くらいかかると思うのであれば4~5月など早めに勉強を開始するようにしましょう。

勉強時間の確保が難しい人は試験1年前から勉強を始めましょう。
具体的な勉強の進め方は以下のとおりです。
①1月~6月|基礎知識を固める
1月~6月は過去問やテキストを使って基礎知識を固める時期です。過去問を最低3回~5回繰り繰り返しましょう。
最初から完璧に理解しようとしなくても大丈夫。とりあえず、まずは問題に慣れることが重要です。気にせずに過去問を解いていきましょう。
以下が過去問を使ったおすすめ勉強方法です。
- 過去問(1回目)
・テキストを読んですぐに過去問
過去問(2回目)
・過去問を解いて間違った箇所を解説とテキストで学習
過去問(3回目)繰り返し
・過去問を解いて間違った箇所を解説とテキストで学習
科目ごとに「テキストを読む⇒過去問を解く」を繰り返していく方法が飽きもこなくておすすめです。テキストと過去問は同じ出版社のものをセットで購入してください。テキストと過去問がリンクしていないと上手く勉強ができません。

8月までには最低3回は過去問を周回しましょう。
②7月~8月|苦手分野の克服
7月~9月は苦手分野を重点的に学習する時期です。ここでも過去問を使って学習を進めていきます。3~5回過去問を解くと苦手分野が浮き彫りになります。過去問で連続して不正解になっている問題に絞って学習していきましょう。
具体的には以下のとおりです。
- 過去問(4回目)
2回目、3回目で連続不正解の問題だけ解く
過去問(5回目)繰り返し
3回目、4回目で連続不正解の問題だけ解く

この時期では正解率が高い問題は学習しなくて大丈夫です。
4回目、5回目も不正解だった問題は完全に理解ができていない問題です。特に苦手分野が頻出問題だった場合は必ず克服するように注意しましょう。
苦手分野を重点的に学習できたら一通り合格に必要な最低限の基礎知識は身についたと言える状態です。

もし、苦手な箇所が出題率が低い問題の場合は、深追いしなくて大丈夫です。
③9月|演習問題と模擬問題で自己分析
9月からは演習問題や模試を受けて学習を進めていきましょう。ここまでの学習で最低限合格に必要な知識は身についているはずです。あとは、その知識を応用できるかが合否の分かれ道となります。
演習問題や模擬試験で学習するメリットは以下のとおりです。
- 現状の実力の確認
- 知識を応用できているか
- あいまいで覚えている箇所はないか
- 苦手分野の分析・克服
- 時間配分の確認
管理業務主任者試験に何回も落ちてしまう人の原因は知識の応用ができていないことです。過去問は完璧なのに、初めて見る問題だと全く正解ができないという状況がよく起こります。試験直前期で慌てないためにも、この時期でしっかり知識を定着させていきましょう。

必ず演習や模擬試験を利用しましょう。
④直前期|予想問題で差をつける
この時期は出題頻度が高い論点を徹底的に学習する時期です。本試験では出題頻度の高い問題をいかに取りこぼしなく正解できるかが合格するための秘訣です。
予想問題を利用するメリットは以下のとおりです。
- 出題頻度の高い論点を網羅できる
- 予想問題から出題されることがある
- 試験日前の要点チェックとして活用できる
直前期までに克服ができなかった苦手分野は深追いせずに諦めましょう。苦手分野で1点を取るよりも、他科目で確実に1点取ることの方が重要です。出題頻度の高い問題の中であいまいになっている箇所を徹底的に潰してください。
予想問題は、市販のものではなく資格学校が提供しているものが的中率も高くておすすめです。良質な予想問題で学習できるかどうかが本試験での正解率に直接影響します。

私は資格学校が提供する予想問題を活用しました。学習した内容が試験に出題されたのでとても助かりました。
初心者が早めに勉強を始めるべき理由

初心者の人が独学で勉強する人が宅建に合格するためには、試験の1年前から勉強を始めることを強くおすすめします。
早めに勉強を始める必要性
宅建は非常に広い出題範囲でそれぞれが専門的な知識を要求します。まずは、試験に合格する為にはこの広範囲な知識の習得と理解が必要です。
管理業務主任者試験の科目は以下のとおりです。
| 科目 | 出題数 |
| 民法(権利関係) | 約14問 |
| 法令上の制限 | 約8問 |
| 宅建業法 | 約20問 |
| 税・その他 | 約3問 |
| 免除科目 | 5問 |
このような広範囲な知識を身につけるには、十分な勉強時間が必要です。 早めに勉強を始めることで、試験範囲全体をじっくりと学習して、復習や苦手分野を克服する時間も確保できます。
また、時間的な余裕があることで焦らずに学習できるため、精神的にも安定した学習計画を立てることができます。

精神的に安定できる環境で勉強をしましょう。
早めに勉強を始めるメリット
早めに勉強を始めることで以下のようなメリットがあります。
- 十分な知識の習得
- 復習と演習の時間確保
- ストレスの軽減
- 予期せぬ出来事への対応
①十分な知識の習得
管理業務主任試験は専門的な知識が求められます。 早めに勉強を始めることで、試験範囲全体をじっくりと学習する時間を確保できます。 また、試験に自信を持って臨むことができます。
②復習と演習の時間確保
早めに始めることで、試験までの期間内に復習や演習の時間を十分に確保することができます。これらの学習行うことで知識の定着度が確保されます。
③ストレスの軽減
最後になってすぐに勉強すると、ストレスがたまりやすくなります。 早めに勉強を始めることで、余裕のある学習スケジュールで計画的に取り組むことができます。直前期で勉強が進んでいないと焦ってしまって自信を持って試験に臨むことができなくなります。
④予期せぬ出来事への対応
試験前に予期せぬ出来事(病気や急な仕事の忙しさなど)が起きても、十分な時間があれば対応する余裕が生まれます。予期せぬ事態に対しても柔軟に対応することができます。
宅建試験は出題範囲が広いため、早めに勉強を始めることが重要です。試験の合格には広範な知識の習得と理解が求められますので、試験の1年前からの勉強をおすすめします。早めの準備により、十分な学習時間や復習・演習の時間を確保することができ、ストレスを軽減して自信を持って試験に臨むことができます。
【3回落ちた私が語る】宅建に受かる気がしない人の共通点と打開策!
超簡単!1日30分で基礎知識を習得
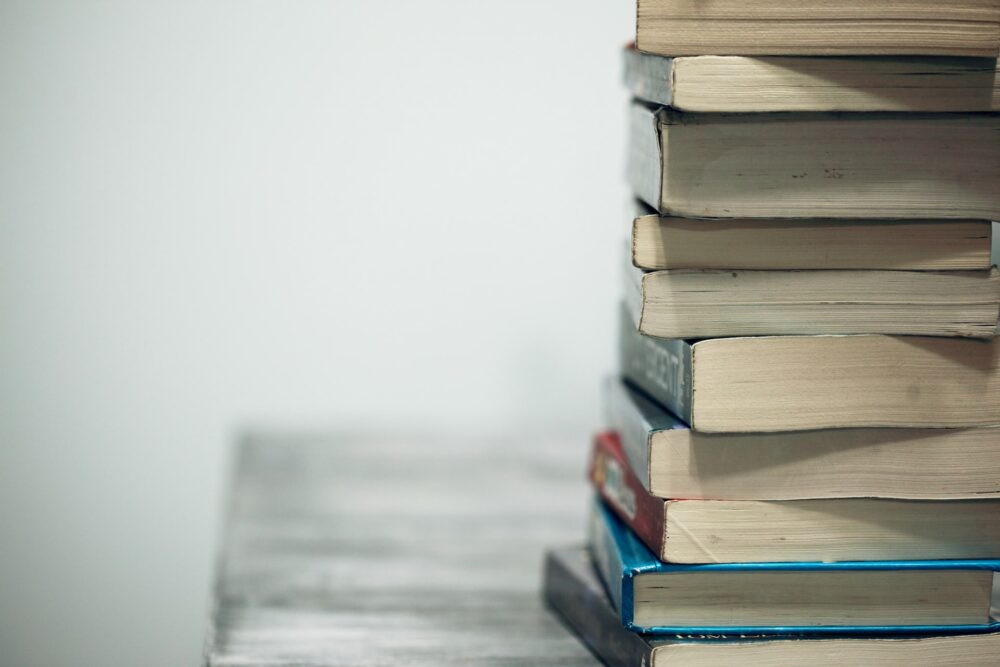
できるなら過去問集を2~3周は学習して知識を定着させたいところですが、なかなか時間の確保が難しい人もいるかと思います。そんな人のために最低1回は過去問集をやりきることができるスケジュールを紹介します。
平日は1日5問、休日は10問を日課にする
1月から6月の間にテキストと過去集で基礎知識を固めましょう。7月までには基礎知識を固めてそれからは苦手分野の克服と応用を学習していくスケジュールが理想的です。
- 1月~6月|テキストと過去集
- 7月~8月|苦手分野の克服
- 9月前半|総仕上げ
- 9月中旬|模擬試験
- 10月|本試験
過去問10年分の過去問集は一般的に600問程度で収録されていることが多いので、平日は1日5問、土日で20問を日課にすれば約3カ月程度で最低でも1回は過去問集をやりきることができます。

平日は1日5問だけでよいので、30分程度の時間があれば大丈夫!
合格者は早くから勉強を始めている

宅建試験で不合格になってしまう原因は「勉強不足」。しっかりと学習さえできれば合格できる資格であるはずなのに多くの人が試験に失敗してしまうその理由は十分な学習時間が確保できていないことです。
宅建試験の難しさ
宅建試験は非常に広い出題範囲でそれぞれの科目で専門的な知識を要求します。試験に合格する為にはこの広範囲な知識の習得と理解が必要です。
宅建試験の科目は以下のとおりです。
| 科目 | 出題数 |
| 民法(権利関係) | 約14問 |
| 法令上の制限 | 約8問 |
| 宅建業法 | 約20問 |
| 税・その他 | 約3問 |
| 免除科目 | 5問 |

学習範囲が広いので十分な時間をかけて学習することが必要です。
初心者は1年前から勉強が理想
初心者の人が試験の1年前から勉強を始めるべき理由は以下のとおりです。
- 広範囲な知識の習得が必要
- 復習のための時間の確保が必要
- 問題演習による知識の定着が必要
①広範囲な知識の習得が必要
試験は分野全般にわたって広い知識をが問われます。初心者の人がこの広範囲の知識を習得するためには、1年程度の準備期間が必要です。
②復習のための時間の確保が必要
専門的な知識を確保させるには、定期的な復習が必要です。試験までの期間を十分に取ることで、学習した内容を復習する時間を確保することができます。
③問題演習による知識の定着が必要
学習した知識を試験形式の問題で取り組むことで、本試験の対策ができます。本試験で初めて見る問題だと全く正解ができないという状況がよく起こります。試験本番で焦らない為に問題演習にも十分な時間が必要です。
具体的な勉強方法
試験勉強は自分の学習スタイルやペースに合わせて調整することが大切です。しかし初心者の人が独学で挑戦する場合は、なるべく早い段階から勉強を始めましょう。
おすすめの勉強スケジュールは以下のとおりです。
- 【1~6月】テキストの読み込みと過去問の周回
- 【7月~8月】苦手分野の克服
- 【9月~】総仕上げ
- 【直前期】予想問題で知識の積み上げ
宅建試験の試験日は10月の第3日曜日です。3ヶ月で合格できそうであれば7~8月頃に勉強を開始しても間に合います。半年くらいかかると思うのであれば4~5月など早めに勉強を開始するようにしましょう。しかし、初心者の人は余裕を持って1年前から勉強を始めることをおすすめします。

勉強時間の確保が難しい人も試験1年前から勉強を始めましょう。
宅建は過去問だけじゃ無理?独学でつまずく人が知らない合格の本質を解説!
時間がない人こそ通信講座を検討してみる
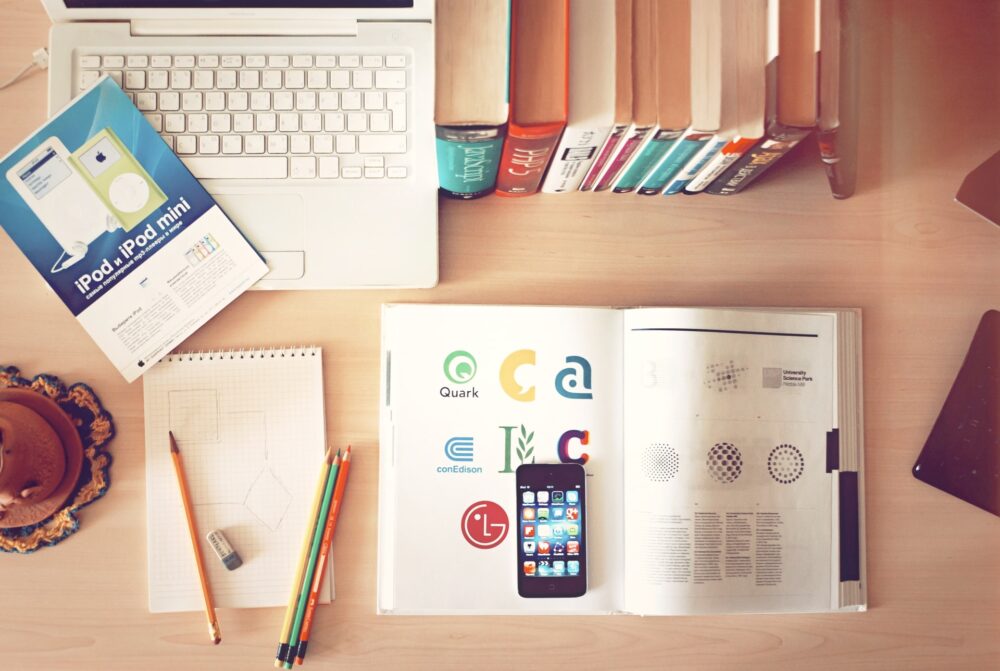
この記事では、初心者が独学で合格を目指したい場合は試験の1年前から勉強を始めることをおすすめさせていただきました。
独学で合格を目指すことは可能ですが、何度もテキストと過去問を読み込むなど想像以上に学習時間を確保する必要があるので効率的だとは言えません。
そのため、独学で短期間で合格することは非常に難しく、早めに勉強を始めることがとても大切になります。もし、独学が不安であれば通信講座の利用も検討してみましょう。

通信講座なら講師が作成したテキストや動画で、重要ポイントをわかりやすく解説してくれるた効率よく学習することが可能です。
通信講座のメリットは以下の通りです。
- 用語や法律の定義や内容を解説してくれる。
- 用語や法律が何を目的としているか、何を規制しているかを把握できる。
- 用語や法律がどのような場面で適用されるか、どのような効果があるかを解説してくれる。
- 重要なポイントや覚え方などを教えてくれるため、効果的に学習できる。
特に法令問題は難しいと感じるかもしれませんが、基礎知識をしっかりと身につけて、問題文の読み方や解答方法を習得すれば、合格に近づくことができます。
少しでも独学に不安を感じたら、無理せず通信講座なども検討しましょう。
Warning: Array to string conversion in /home/xs361114/kangyou-sikaku.com/public_html/wp-content/plugins/simple-blog-design-for-meril/inc/blocks/blog-card/view.php on line 24