
- 頑張っているのに、結果が出ない。
- 過去問は解けたはずなのに、本番では歯が立たなかった。
- どう勉強していいか、もうわからない…
管理業務主任者試験に挑戦する人の多くが、こうした壁にぶつかります。私自身もその一人でした。何度も過去問を繰り返し、努力を重ねたつもりなのに、結果は不合格。あの時の絶望感は今でも忘れられません。
この試験は、ただ暗記するだけでは太刀打ちできません。「ここまでやったから大丈夫」という思い込みが、逆に落とし穴になってしまうのです。
この記事では、独学でつまずいた私の体験をもとに「なぜ合格できないのか」という共通の失敗パターンを明らかにして、合格へつなげる学習のヒントを解説します。

「受かる気がしない」そんな不安を抱えているなら、今こそ学習方法を見直すチャンスです!
👉 「最短で解決策を知りたい」という方は、先に 通信講座比較記事 をチェックしてもOKです。
区分所有法と標準管理規約の相違点を理解できていない

管理業務主任者試験では、毎年のように「区分所有法」と「標準管理規約」の相違点を問う問題が出題されます。
- 区分所有法とは
- マンションで円滑な共同生活を送るための法律。必ず守るべき最低限のルール。
- 標準管理規約とは
- 区分所有法を補完し、実際のマンション管理組合の運営を支える“ルールブック”。

区分所有法と標準管理規約の違いを理解できていない人が多い!
チェックポイント
どちらも似ているため「なんとなく同じ」と捉えてしまいがちですが、細かな違いが合否を分ける。
区分所有法と標準管理規約の違い
標準管理規約は区分所有法をベースにして作られたものなので内容が非常によく似ています。
以下は、よく狙われる相違点の例です。
| 項目 | 区分所有法 | 標準管理規約 |
| 総会(集会)の招集期間 | 1週間前 | 2週間前 |
| 共用部分の持分割合 | 内のり計算 | 壁心計算 |
| 共用部分・施設の使用制限 | 区分所有者会の決議で定める | 管理規約で定める |

とくに議決権の相違点は狙われやすい!
チェックポイント
毎年、管理業務主任者試験では区分所有法と標準管理規約の相違点がひっかけ問題として出題されています。必ず本試験までには押さえておきましょう。
過去問の丸暗記に頼っている

試験で得点できない原因は「過去問を丸暗記している」こと。自分ではそういうつもりが無くても無意識に答えだけを覚えてしまっていることに注意が必要です。
本番では文章を少し変えたり、応用させたりする問題が出題されます。論点の理解が不十分だと「こんな問題、見たことがない…」と手が止まってしまいます。
過去問を解くことは試験対策に欠かせないことですが、あくまでも過去の出題傾向を示す資料として利用しましょう。
- 解答の根拠を必ず確認する
- 頻出論点を把握して重点化する
- 本番を想定して「なぜこの答えになるのか」を意識する

過去問は出題傾向を示す資料!
チェックポイント
特に法令系の問題は要注意。管理業務主任者試験の約6割は法令系の問題で構成されているので。論点そのものを理解しておかないと独特な表現やひっかけに翻弄されてしまいます。
👉 関連記事:管理業務主任者試験で頻出する用語と効果的な覚え方
完璧主義に陥っている

管理業務主任者試験は出題範囲が非常に広いため、出題傾向を分析した学習が重要です。「勉強したところが全然出題されなかった」と本番で嘆く受験者も多く、何度も失敗してしまう人の原因の一つが「どこから出題されても大丈夫なように」完璧を目指していることです。

私も「出題頻度の低い論点」を必死に学習しましたが、結局本番では出題されず時間を無駄にしました。
チェックポイント
完璧は求めずに「出題頻度の高い論点を確実に取る」こと。
建築・設備で高得点を狙っている

管理業務主任者試験の約11問が建築・設備から出題されています。
| 科目 | 出題数 |
| 設備系法令 (建築基準法) | 約5問 |
| 建築・設備 | 約6問 |
建築・設備分野は暗記中心で学びやすい一方、範囲が膨大で新傾向問題も多く出題されます。まず、建築知識がない人が得点を伸ばすことは無理です。
毎年、はじめて問われるような問題が多くこの科目を重点的に学習していると「過去問で覚えた問題が出題されなかった」という結果に陥ってしまいます。

過去問を完璧にしても、本番で7~8割取れれば十分と考えましょう。
チェックポイント
出題範囲が広すぎるため頑張った分だけ得点が伸びるような科目ではないことに注意。「この分野で満点を狙う」のではなく、「得点源を確保する」戦略が必要です。
苦手分野から逃げている
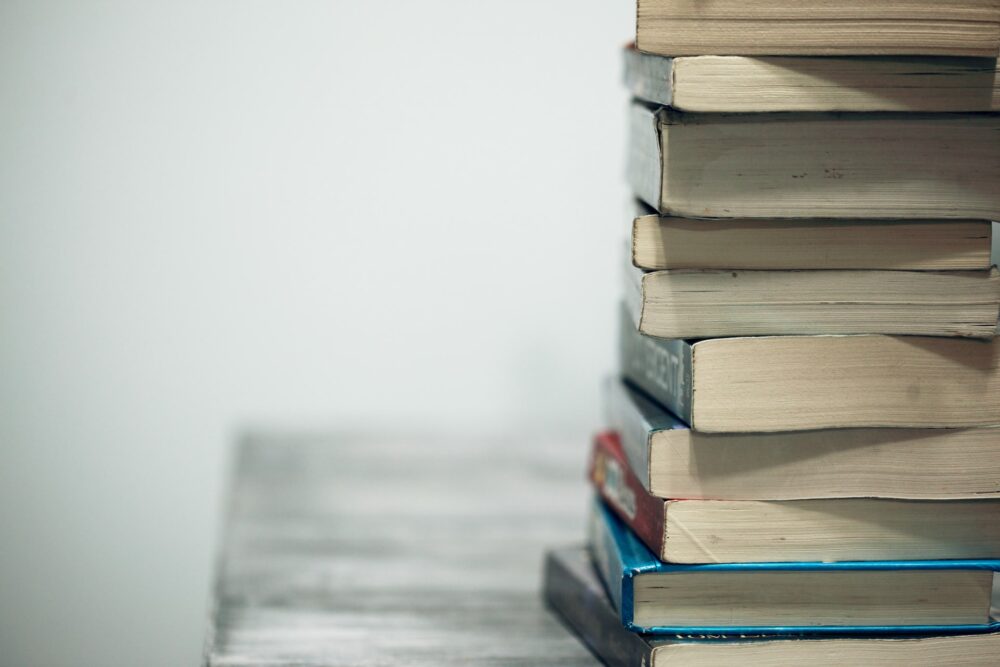
管理業務主任者試験では、法律や建築、区分所有法などの幅広い分野から出題されるため、苦手科目を避けると合格点に届きません。なぜなら、試験では各分野の出題比率が決まっているので苦手分野を無視していると合格点に届かない可能性が高いからです。
| 科目 | 出題数 |
| 民法・その他の法令 (宅建業法・品確法) | 約11問 |
| 区分所有法 | 約9問 |
| 標準管理規約 | 約5問 |
| マンション管理適正化法 | 約5問 |
| 標準管理委託契約書 | 約6問 |
| 会計 | 約3問 |
| 設備系法令 (建築基準法) | 約5問 |
| 建築・設備 | 約6問 |

苦手分野が増えるほど試験を突破できる確率が低くなることに注意!
チェックポイント
管理業務主任者試験は100人が挑戦して20人しか合格できない難関資格。合格ライン付近ではほぼ同じ実力の受験者がひしめきあっているので、わずか1点で合否が決まってしまいます。
まとめ|「受かる気がしない」と思ったら戦略を変えよう
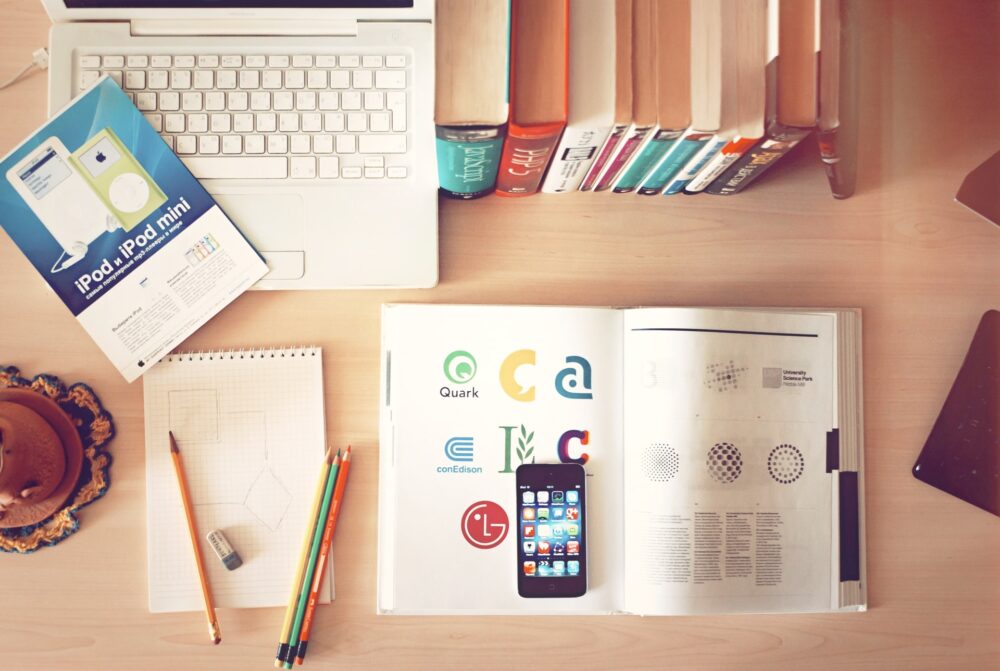
管理業務主任者試験に落ちてしまう人の5つの特徴は以下のとおりです。
- 論点を理解せず丸暗記している
- 区分所有法と標準管理規約の違いをあいまいにしている
- 完璧主義で出題頻度の低い分野に時間を割いている
- 建築・設備で高得点を狙いすぎている
- 苦手分野から逃げている
そして最後に大きな落とし穴となるのが、独学にこだわりすぎていることです。
私自身、最初は「独学でなんとかなるだろう」と思って挑戦しました。しかし、参考書をいくら読み込んでも「区分所有法と標準管理規約の違い」を曖昧なまま捉えてしまい、本番では見事にひっかかってしまいました。
「これだけ勉強したのに、なぜ正解できないんだ…?」試験直後のあの絶望感は今でも忘れられません。
二度の不合格を経てようやく気づいたのは、自分だけの理解には限界があるということです。そこで三度目の挑戦では思い切って通信講座に切り替えました。
プロが体系的に整理したカリキュラムや、試験に出やすいポイントをズバリ押さえた解説を受けることで、それまで曖昧だった知識が一気にクリアになり、無事に合格することができました♪

通信講座なら、独学では気づきにくい“落とし穴”もきちんとカバーしてくれます。
特に以下のような方は、早めに通信講座を検討するのがおすすめです。
- 学習時間の確保が難しい人
- 出題傾向の分析に自信がない人
- 独学で過去に失敗した経験がある人

「もし今年も落ちてしまったら、また1年先延ばし…。」でも通信講座なら、効率よく最短で合格を狙えます。
もし「受かる気がしない」と不安を抱えているなら、それは学習方法を変えるサインです。
来年また同じ後悔をしないために。今こそ戦略を変えてみましょう♪
今すぐ確認したい