- 「35条と37条の違いがごちゃごちゃになってしまう…」
- 「契約前?契約後?どっちがどっちか混乱する」
- 「過去問では覚えたはずなのに、ひっかけに引っかかってしまう」
宅建試験を勉強していると、必ずつまずくポイントのひとつが「35条書面」と「37条書面」。実際、このテーマは毎年出題され、合否を分ける重要ポイントです。
ここをスッキリ整理できれば、本番でひっかけ問題に強くなり、得点源にできます。
知識を確認するだけでなく、「本番までに合格点に届くか不安…」という方はこちら▶ 宅建試験直前期の追い込み方!残り1か月で合格点に届かせる勉強法
そこで本記事では、35条書面と37条書面の違いから、試験で狙われやすいポイント、最新の電子交付制度、さらに私自身の独学失敗談も交えて効率的な勉強法を解説します。
35条書面とは?試験で必ず出る“契約前の書面”

35条書面の位置づけ
「35条書面」とは、重要事項説明書のことです。宅建業法第35条により、契約を締結する前に、宅建士が買主や借主に対して重要事項を説明し、書面を交付する義務があります。
35条書面の内容
主な記載事項は以下の通りです
- 登記簿に記載された権利関係
- 法令上の制限(都市計画法、建築基準法など)
- 私道負担・接道・ライフラインの状況
- 契約解除や違約金に関する事項
- 代金・交換差金・賃料・支払いの方法等

宅建士が口頭で説明を行い、契約前のトラブルを防止することが目的です。
37条書面とは?試験で狙われる“契約後の書面”

37条書面の位置づけ
「37条書面」とは、契約書面交付の義務がある書面です。契約の成立・締結後、宅建業者は依頼者に対してこの書面を交付しなければなりません。
37条書面の内容
37条書面には以下の事項が含まれます。
- 契約当事者の氏名・住所
- 物件の所在地・面積等
- 契約の目的(売買・賃貸借など)
- 契約日・契約期間・引渡し時期
- 代金・賃料・支払方法
- 契約解除・違約金等

契約後、遅滞なく交付すること義務付けられており、契約内容の証拠としての役割を持ちます。
最新法令情報|記名押印と電子交付について

宅建士の押印(記名押印)の要否
35条書面・37条書面ともに、宅建士による記名押印が法令上必要です。手書きの印を必ずしも求められるわけではなく、印刷または電子署名などによる記名が認められています。国の資料にも、「宅建業法第35条及び第37条を含む書面を電子で提供する場合でも、記名を行うこと」が要件の一つとされています。
電子による交付(電子書面/電磁的方法による提供)の制度
2022年5月の法改正により、媒介契約の書面(法34条の2)、重要事項説明(35条書面)、契約書面の交付(37条書面)について、相手方の承諾があれば、紙の交付の代わりに電子的方法による提供が可能となりました。
電子交付の要件(国土交通省マニュアル等に明示されているもの)
- 相手方(買主・借主など)の明示的な承諾を得ること。賃貸・売買取引問わず必要。
- 電子交付する書類の種類を特定すること。どの書面を電子にするかを明確化する必要があります。
- 使用する電子的方法(メール、Web ダウンロード、クラウド等)やファイル形式を承諾時に説明・示すこと。
- 改変防止措置(例えば電子署名+タイムスタンプなど)を備えること。
- 添付書類がある場合、その添付書類も電子交付するならば、書面電子化の要件を満たす必要あり。
35条書面と37条書面の違いを比較

35条と37条は、宅建業法の中でも「契約前」と「契約後」という真逆のタイミングで交付される点が最大の違いです。また、35条は「説明+交付」であるのに対し、37条は「契約内容の証明」が目的であり、説明義務は課されていません。
このように役割がまったく異なるため、試験でも混同しやすいポイントとして毎年のように問われています。
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書面交付) |
| 交付(提供)のタイミング | 契約を締結する前に説明・交付(または電子提供) | 契約の成立または締結後に遅滞なく交付(または電子提供) |
| 目的 | 契約前に物件・条件・リスクを説明して理解を得る | 契約成立内容を証明し、契約内容を明文化する |
| 説明義務 | 宅建士自身が口頭で説明する義務あり | 説明義務は法律上定められていない |
| 宅建士の記名押印 | 必須。電子交付の場合も記名押印(電子署名等)が必要 | 必須。こちらも電子交付の場合は同様に記名押印(電子署名等) |
| 主な内容 | 権利関係、法令上の制限、賃貸借・支払い条件、解除・違約金など | 当事者情報、物件情報、引渡時期・契約期間・支払い方法など |
この比較からわかるように
- 35条は契約前に相手を守るための説明義務
- 37条は契約後にトラブルを防ぐための証明義務
という位置づけになります。

前=35、後=37。さらに「説明あり=35、なし=37」と意識するだけで点数が伸びますよ♪
試験での出題傾向と攻略法
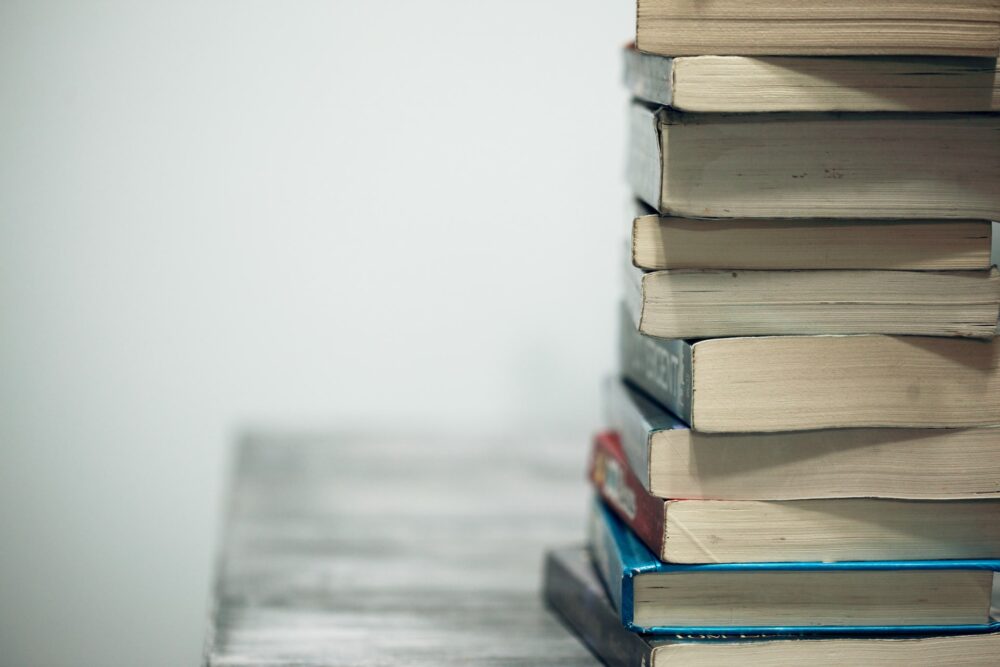
出題傾向
宅建試験では、35条・37条に関する問題がほぼ毎年1〜2問出題されています。特に狙われやすいのは「契約前か後か」というタイミングのひっかけです。
よくあるひっかけ問題
- 「37条書面は契約前に交付すればよい」
→ ✕(契約後) - 「35条書面の交付は宅建士でなくても可能である」
→ ✕(宅建士必須)

このように、基本ルールを逆手に取った出題が多く、「覚えたはずなのに間違える」受験生が続出します。
攻略法
- タイミングで整理する。
→「前=35、後=37」と一言で区別できるように暗記。 - 表や図で視覚的に覚える
→文章で丸暗記するより、表にして見比べると頭に入る。 - 過去問で“ひっかけパターン”をつぶす
→5年分の過去問をやれば、同じようなひっかけが繰り返し出ていることに気づく。

ポイントは、「ただ覚える」のではなく「どう問われるか」を意識して解くこと。これが本番で点数に直結します。
35条・37条は試験でも実務でも超重要!

不動産取引は金額が大きく、生活基盤に直結するため、契約の前後でトラブルが起きやすい分野です。そこで大きな役割を果たすのが35条書面と37条書面です。
- 35条書面は契約前の説明を通じてトラブルを未然防止
- 37条書面は契約内容の証拠として争いを防止
- 電子交付の普及で、オンライン取引でも必須の知識

実務でも試験でも、“セットで理解”することが重要です♪
独学に限界を感じたら通信講座を検討しよう

宅建試験は過去問演習とテキスト学習である程度対応できます。ただし、独学には限界があることも事実です。
実は私自身、独学で挑戦しました。テキストを何周も回し、過去問も解き込んで毎年「理解したつもり」で試験を受け、結局3回連続で不合格。
合格できたのは4回目でしたが、正直に言うと 「最初から通信講座を使っていれば、もっと早く合格できた」 と今でも後悔しています。
読者の皆さんも同じように、こんな悩みを抱えてはいないでしょうか?
- 「過去問を解いても応用問題に対応できない」
- 「実はなんとなくで理解している」
- 「独学だと勉強のペースが崩れがち」
これらは私が独学時代に何度も感じた壁です。そして、合格できない受験生が同じ壁でつまずいています。

だからこそ、通信講座という選択肢も検討してみてほしいです。
通信講座のメリット
- 最新の法改正を反映したテキスト・解説
- ひっかけ問題の“出題パターン潰し”を徹底できるカリキュラム
- 講師に質問できるサポート体制
「独学 or 通信講座」のどちらを選ぶかは自由ですが、少なくとも私は「講座を使っていれば3年も早く合格できた」と断言できます。
👉 無料体験や資料請求から始めればリスクゼロ。比較して、自分に合う講座を見つけましょう。
▶ 宅建おすすめ通信講座3選【独学失敗者が比較】
まとめ:宅建35条と37条の違い

本記事では、宅建業法における35条書面と37条書面の違いを現行法(押印・電子提供制度含む)に則って解説しました。ポイントを改めて整理すると
- 35条書面=契約前の重要事項説明書、37条書面=契約成立後に交付する契約内容の書面
- どちらも宅建士による記名押印必須。手書き押印でなくても電子署名等の電子的措置で代替可能
- 2022年5月の法改正で、相手方の承諾があれば書面に代えて電子的方法による交付が可能に
- 電子交付には承諾・方法・改変防止措置など複数の要件がある
もし、独学でこれらを完全に理解して整理するのが不安な場合は、通信講座のサポートを活用するのも有効です。
最新の制度も含めた講座を選べば、試験対策がぐっと効率的になります。