- 模試の点数が全然伸びなくて、このまま落ちるんじゃ…
- あと何点取れば受かるのか、誰か教えて!
- 今の勉強法が正しいのか不安で仕方ない…
「試験が近づいているけど、点数が伸びない」「模試で思うような結果が出ない」宅建試験の直前期では多くの受験生がこうした不安や焦りを感じています。私もまさにそうでした。
しかし、焦って無計画に勉強を進めるのは逆効果。合格ラインを正しく理解し、直前期に何を優先するべきかを押さえれば、今からでも合格は十分に狙えます。
この記事では、宅建試験の合格ラインの傾向と、試験直前に集中すべき勉強法を詳しく解説します。

直前期こそ合否を分ける勝負所です!
宅建試験の合格ラインとは?過去データから見る目標点

宅建の合格基準は“相対評価”
宅建試験の合格ラインは毎年一定ではありません。実は、試験の難易度や受験者の平均点に応じて「相対評価」で決まります。つまり、50点満点中「必ずこの点数を取れば必ず合格」という基準はありません。
合格ラインの平均と安全圏
| 年度 | 合格点 |
| 2013年度 | 33点 |
| 2014年度 | 32点 |
| 2015年度 | 31点 |
| 2016年度 | 35点 |
| 2017年度 | 35点 |
| 2018年度 | 37点 |
| 2019年度 | 35点 |
| 2020年度 | 38点 |
| 2021年度 | 34点 |
| 2022年度 | 36点 |
| 2023年度 | 35点 |
| 2024年度 | 37点 |
以上のように、過去10年の合格ラインを見てみると、概ね35点前後が基準となっており、最も多いのは35〜36点。ただし年によっては33点だったこともあれば、38点という高水準の年もあります。
- 合格点の目安:35点前後
- 安全圏ライン:36〜38点

私も本番では「38点」を目標に設定して安心感を持って挑みました。
科目別の得点戦略
宅建試験では以下の4分野から出題されます。
| 分野 | 出題数 | 得点戦略 |
| 宅建業法 | 20問 | 18点以上を目標 |
| 民法(権利関係) | 14問 | 難問多め。「拾える問題」を取る |
| 法令上の制限 | 8問 | 暗記で対応可。5点前後を狙う |
| 税・その他 | 8問 | バラつき大きめ。4点程度を確保 |
宅建試験で特に重要なのが「宅建業法」。ここは点数が取りやすく、合格者の多くが18点以上を得点しています。逆に「民法」は難解な問題が多いため、最初から完璧を目指すよりも「拾える問題を確実に取る」ことが大切です。

私が合格できた時も宅建業法は全問正解でした。
直前期にやるべき5つの対策

① 過去問のやり直しを徹底する
過去問は最強の教材です。ただし「一度解いて終わり」や「なんとなく解く」では意味がありません。必ずどうしてその答えになるのか?を理解しながら復習をしましょう。
- 同じ問題を3回以上解く
- 間違えた問題をピックアップする
- 解説を読んで“なぜ間違えたのか”を言語化する

このプロセスを踏むことで、理解が深まり、本番でのミスを減らせます。
② 宅建業法を完璧に仕上げる
宅建業法は配点が高く、過去問との類似問題も多いため、点を取りやすい分野です。

このあたりを条文レベルで押さえれば、業法は得点源になります。
③ 苦手分野を絞って潰す
「全科目をまんべんなく」よりも、「苦手分野を集中して克服」するほうが直前期には効果的です。つい不安な気持ちから、既に理解している論点も学習してしまうことがります。直前期では毎回正解できている箇所は学習せずに正解率が低い問題に絞って学習しましょう。
- 正解率が低い箇所を優先して学習する
- 苦手箇所でも出題率が低い問題は「捨て問」にする

全部覚えるのではなく、得点につながる論点だけを短期間で集中的に学習しましょう!
④ 模試や予想問題を活用する
直前期には市販の模試や予想問題集を活用しましょう。以下の点に意識を向けると効果的です。
- 本番と同じ時間帯に解く
- 本番と同じ筆記用具を使う
- 過去問と違う言い回しでも解けるのかを確認する
- 結果よりも“復習”を重視する
👉 直前期の過ごし方はこちらで解説しています
▶ 宅建試験直前期の追い込み方!残り1か月で合格点に届かせる勉強法

予想問題でうまく得点できなくても落ち込まなくて大丈夫です。解けなかった問題の分析・復習することで得点力が身に付きます!
⑤ 試験当日を想定したメンタルトレーニング
知識だけでなく、試験当日の精神状態も結果に大きく影響します。
- 試験前のルーティンを決めておく
- 昼ご飯やトイレのタイミングも想定する
- 前日から試験会場近くのホテルを予約するのも手

本番で「いつも通りの力」が出せる準備をしましょう。
ここが狙われやすい!要注意の出題ポイント

頻出論点と近年の傾向
近年の傾向として、次のようなテーマがよく出題されています。
- 個数問題(正しいものはいくつあるか)
- 判例知識を問う応用型民法問題
- 宅建業法の法改正

特に改正点は高確率で出題されるため、各年度の法改正情報は要チェックです!
今からでも間に合う!直前期スケジュール
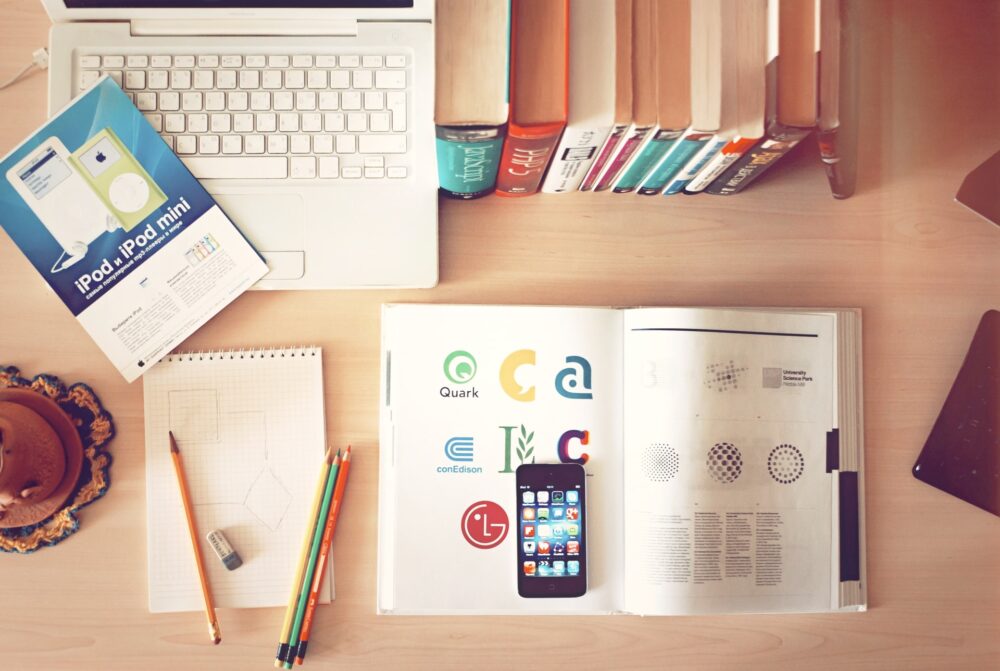
残り1ヶ月・2週間・1週間のやることリスト
残り1カ月
- インプット8割、アウトプット2割
- 全体の理解と過去問1周目の整理
残り2週間
- 苦手論点の集中対策
- 過去問2周目+予想問題
残り1週間
- 全分野の総復習
- 本番を意識した演習と休養のバランス
毎日の勉強時間と科目配分の目安
- 平日:1〜2時間(朝・夜に分けて)
- 休日:3〜5時間(集中ブロック学習)
- 宅建業法:毎日1時間は確保

科目別では「宅建業法>民法>法令制限>税・その他」の順で優先しましょう。
【実体験】宅建合格者が語る「直前期の過ごし方」

実際に合格した人たちの体験談から、直前期の過ごし方のヒントを見てみましょう。
「毎朝30分、宅建業法の過去問を解いたのが習慣化できた」
「民法は完璧にしなくてOK。解ける問題だけに集中した」
「模試の点が伸びなかったけど、本番で37点取れて合格できた」

大切なのは、「完璧主義にならないこと」と「確実に取れる点を落とさないこと」です。
まとめ|合格ラインを知れば直前期も戦える

宅建試験は誰にとっても不安でいっぱいですが、合格ラインを見据えた戦略的な学習をすれば、合格の可能性は飛躍的に高まります。
- 合格点は 35点前後、安全圏は38点
- 業法で18点を確保し、残りは「落とさない」戦略
- 直前期は「過去問・苦手克服・模試」で仕上げる

直前期は誰でも焦ります。でも「あと何点必要か」を把握し、優先順位を決めれば必ず戦えます!
👉 残り1か月で“合格点に届かせる”具体ステップはこちら
▶ 宅建試験直前期の追い込み方!残り1か月で合格点に届かせる勉強法
👉 もし「今年は厳しいかも…」と感じたら、来年に備えて通信講座を検討するのも戦略です。
▶ 宅建通信講座おすすめ3選【独学失敗者が比較】