- 宅建と管業、どっちが簡単?
- 働きながらならどっちが現実的?
- 独学でも合格できるのは?
「宅建は簡単」と聞いて始めたのに、全然簡単じゃない。
あるいは、管業に挑戦して「思ったより難しい」と感じていませんか?
結論から言うと、難易度はほぼ同じ。ただし「難しさの種類」が違います。
- ✔ 初心者なら宅建の方が戦略は立てやすい
- ✔ 管理会社勤務なら管業が有利
- ✔ 勉強時間はどちらも300〜400時間が目安
この記事では、合格率・勉強時間・出題傾向の違いから「あなたに合うのはどちらか」を明確にします。

自分に合った資格はどっちか今すぐチェックしてみましょう!
まず結論:難易度はほぼ同じ
| 比較項目 | 宅建 | 管理業務主任者 |
| 合格率 | 15〜17% | 20〜23% |
| 勉強時間 | 300〜400時間 | 約300時間 |
| 出題数 | 50問 | 50問 |
| 合格ライン | 35〜37点 | 35〜37点 |
| 難しさの特徴 | 得点源を固める力 | 分野横断の安定力 |
数字上は大きな差はありません。
しかし実際に受験すると、「難しさの方向性」がまったく違う試験だと感じます。

一般的に宅建の方が難しいと言われていますが、
どちらも300時間程度の勉強が必要で
簡単に合格できる資格ではないことが言えます。
合格率で比較|管業の方が高い理由
| 年度 | 管理業務主任者 | 宅建士 |
| 2022年度 | 18.9% | 14.9% |
| 2023年度 | 21.9% | 17.2% |
| 2024年度 | 21.3% | 18.6% |
平均合格率
- 宅建:15〜17%
- 管業:20〜23%
では、なぜ管理業務主任者のほうが合格率が高いのでしょうか?
それは、管業の受験者はすでに宅建士やマンション管理士などの資格を持っている人が多いからです。
- ✔ 管業受験者は宅建取得者が多い
- ✔ すでに業界経験者が多い
つまり受験者レベルが違います。

合格率だけで「管業の方が簡単」と判断するのは危険です。
※宅建の難易度について、試験データをもとに詳しく知りたい方は
▶宅建の難易度を詳しく見る
※管業の試験傾向をさらに詳しく知りたい方は
▶管業の難易度を詳しく見る
勉強時間で比較|どちらも約300時間以上
| 資格 | 目安勉強時間 |
| 宅建士 | 300〜400時間 |
| 管理業務主任者 | 約300時間 |
働きながらだと、
- 1日2時間 × 約5〜6ヶ月
- 週末中心なら半年以上
これが現実的な目安です。
ただし、宅建は“得点源が明確”なため、戦略次第で時間効率を上げやすい試験。
一方で管業は、複数分野を横断的に対策する必要があり、苦手分野があると想定より時間がかかることがあります。

つまり、必要時間は同じでも、時間の使い方が違う。
ここがポイントです。
出題範囲の違いが“難しさ”を決める
宅建と管理業務主任者は、どちらも50問の試験です。
しかし、出題構造がまったく違います。
難易度の差は「合格率」よりも、この出題範囲にあります。
宅建は“戦略型”の試験
宅建は出題の内訳が比較的はっきりしています。
- 宅建業法が20問(最大の得点源)
- 民法(権利関係)が約14問
- 法令上の制限が約8問
特に宅建業法は配点が安定しており、重点的に対策すれば点を伸ばしやすい科目です。
つまり宅建は、
👉 得点源が明確で戦略が立てやすい“攻略型”の試験と言えます。
※宅建の難易度について、試験データをもとに詳しく知りたい方は
▶宅建試験の攻略法を詳しく解説
管業は“総合型”の試験
一方で、管理業務主任者は分野が横断的です。
- 区分所有法
- 標準管理規約
- 管理委託契約
- 設備・会計
- 各種法令
複数分野からバランスよく出題されるため、
得点源が一点に集中しにくくて、苦手分野があると失速しやすい特徴があります。
つまり管業は、
👉 横断的に得点できる総合力が求められる試験です。
※管業の試験傾向をさらに詳しく知りたい方は
▶管理業務主任者の出題傾向を解説

私は宅建合格後に管業へ挑戦しましたが、
体感では管業の方が難しく感じました。
合格ラインの意味|約70%正解が必要
| 資格 | 平均合格ライン | 最近の合格ライン |
| 管業 | 35~37点 | 35~38点 |
| 宅建 | 35~37点 | 35~37点 |
宅建も管理業務主任者も、合格ラインは50点中35〜37点。
つまり、約70%の正解率が必要です。
「合格率が20%前後」と聞くと難関に感じますが、本質は“上位何%か”ではありません。
「安定して7割取れる実力があるかどうか。」

難易度の差よりも、
「7割を取り切る設計ができるか」が合否を分けます。
あなたはどっちタイプ?簡易診断
まずは直感でチェックしてみてください。
宅建タイプ
- □ 得点源を固める勉強が好き
- □ 勉強計画を立てるのが得意
- □ 不動産業界未経験
- □ 法律の暗記に抵抗がない
→ 2つ以上なら宅建タイプの可能性が高いです。
管業タイプ
- □ 管理会社勤務
- □ 実務とリンクさせたい
- □ 分野を横断して理解するのが得意
- □ 設備や会計にも抵抗がない
→ 2つ以上なら管業タイプの可能性が高いです。
※あくまで傾向チェックです。当てはまったタイプから読み進めてみてください。
こんな人は宅建向き
- 不動産未経験
- 転職目的
- 独学志向
- 法律が苦ではない
宅建を取得するとどんなメリットがあるのかは、
👉 宅建士を取るメリットを4冠資格保有者が解説
宅建は対策が明確で、独学でも再現性が高い資格です。
こんな人は管業向き
- 管理会社勤務
- マンション管理志望
- 宅建取得済み
- 設備・実務に抵抗がない
業務直結型の資格なので実務者には相性が良い試験です。
働きながら取るならどっち?
働きながらなら、
- 勉強時間を“固定化”できる人 → 宅建
- 業務とリンクさせられる人 → 管業

宅建は「試験対策」と割り切りやすい構造。
管業は実務とリンクする人ほど有利です。
結局どっちを選ぶべき?
最終判断はこれでOKです。
| あなたの目的 | おすすめ |
| 転職 | 宅建 |
| 管理業界特化 | 管業 |
| 独学中心 | 宅建 |
| 実務直結 | 管業 |
迷ったら、まずはそれぞれの特徴をもう一度整理してみてください。
▶ 宅建を取得するメリットを不動産4冠資格保有者が解説
▶管理業務主任者が向いてる人・向かない人を徹底解説!

迷った場合は、キャリアの選択肢が広い宅建を選ぶ人も多いです。
業界未経験でも評価されやすいからです。
まとめ|どっちが簡単かより「どっちが合うか」
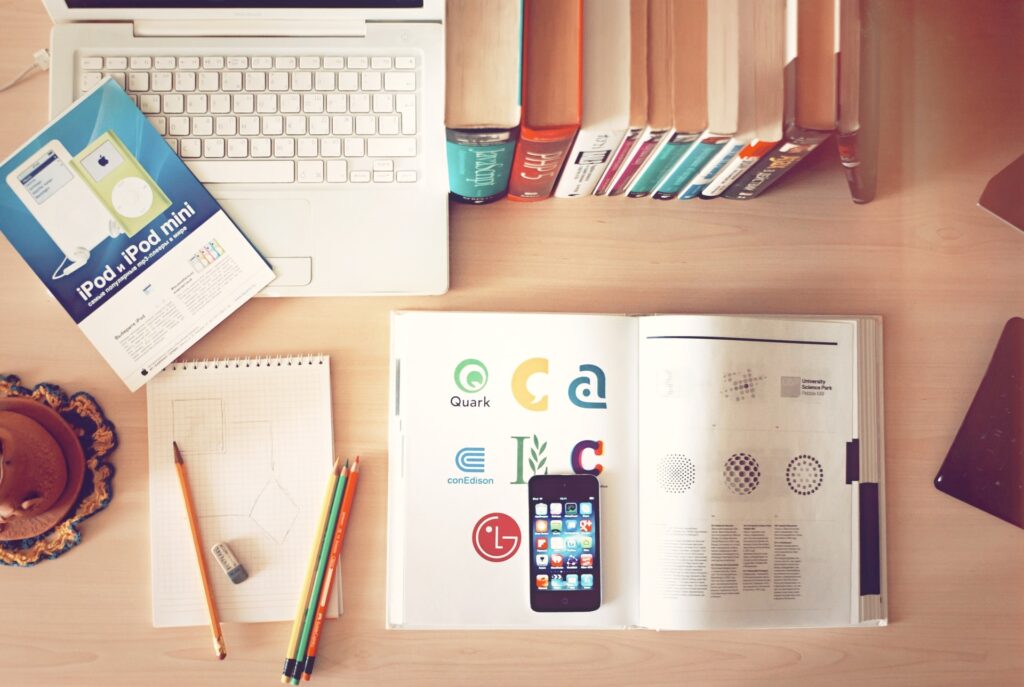
「どっちが簡単か?」と聞かれれば、答えは“ほぼ同じ”。
でも「どっちが合うか?」で考えれば、答えは変わります。
- 合格率に大きな差はない
- 勉強時間も約300〜400時間
- 合格ラインは約70%
違いがあるとすれば、それは試験の構造です。
- 宅建は“戦略型”
- 管業は“総合型”
どちらが簡単かは一概には言えません。
大切なのは、「自分に合った試験を選べるかどうか」です。
迷ったら、まずは目的を整理してみてください。
試験の難易度よりも、自分との相性の方が合否に直結します。
- 転職やキャリアの土台を作りたい → 宅建
- 管理業界で専門性を高めたい → 管業
正しい戦略で取り組めば、どちらも十分に合格を目指せる資格です。
※具体的な講座選びを検討している方は、以下の記事も参考にしてください。
▶ 宅建通信講座の比較を見る
▶ 管理業務主任者の通信講座比較を見る