
- 「もう3回目だけど、また落ちた…。」
- 「働きながらじゃやっぱり難しいのかな…」
- 「自分なりに頑張ってるのに、周りは受かってて焦るだけ…」
宅建試験は、法律や不動産の基本知識など幅広い知識が求められる難易度の高い試験です。
この試験に合格するためには、「試験に落ちてしまう原因」を理解することがとても重要です。
「受かる気がしないと」感じている人は、今と同じまま頑張り続けても失敗を繰り返してしまうことは間違いありません。
私は4度目の試験でやっと合格することが出来ました。しかし、試験に落ちてしまう原因をきちんと理解していればもっと早く試験に合格できたと後悔しています。

私と同じ失敗はしないようにしてください。
この記事では、私が宅建試験に3度失敗した経験から、試験に落ちてしまう人の特徴と原因を解説します。
この記事を読めば、私と同じように「受かる気がしない…」「結果がでない…」と何度も失敗することはありません。

落ちる人の原因を理解して合格を目指しましょう!
過去問だけじゃ合格できない?

試験本番で得点できない原因は主に「過去問を丸暗記している」ことです。自分ではそのもりがなくても無意識に答えだけを覚えてしまっていることに注意が必要です。
過去問は意識をして問題を解かない限り、解答の根拠や論理を理解することが出来ません。過去問だけで満足してしまうと、本番で出題される応用問題に対応できなくなってしまいます。
たしかに、過去問を解くことは試験対策に欠かせないことですが、試験の出題傾向を示す資料として有効に利用しましょう。
過去問を効果的に活用する方法は以下の通りです。
- 過去問を解いた後に、解答の根拠や理論を確認する
- 過去問で頻出されている問題を意識する
- 参考書や疑似問題なども利用する

過去問だけを解いて満足しないように注意してください!
試験本番では過去問と同じ文章では出題されません。きちんと過去問の論点を理解しておかないと、実は過去問と同じ内容を問われているのに「こんな問題は見たことがない…」と失敗してしまう原因になります。

過去問はあくまでも出題傾向を示す資料!
▶「過去問だけじゃ合格できない…」と悩む方は、合格者がやっている具体的な勉強法もぜひチェックしてみてください。👉 宅建は過去問だけじゃ無理?独学でつまずく人が知らない合格の本質を解説
重要な科目を理解していない

宅建試験は出題範囲が非常に広いため、出題傾向と出題頻度を分析した学習が重要です。
「勉強したところが全然出題されなかった」と本番で嘆く受験者も多く、試験に失敗してしまう原因が、どこから出題されても大丈夫なように全科目を均等に勉強していることです。
そして、出題頻度が低い問題を学習してしまい、試験本番で出題されることはなく合格ラインに達しません。
チェックポイント
宅建試験は、いかに出題頻度の多い科目を取りこぼしなく正解できるかが重要。学習時間を出題頻度の多い科目に使う方が得策です。

私は「ここから出題されたらどうしよう」という不安から出題頻度が少ない論点を必死に学習していました。
“合格のカギ”は宅建業法
まず「宅建業法」で8割以上得点できていない人は、非常に厳しい状況であることを認識しておきましょう。
まずは、宅建士試験の出題科目と配点を確認しましょう。
| 科目 | 出題数 |
| 民法(権利関係) | 約14問 |
| 法令上の制限 | 約8問 |
| 宅建業法 | 約20問 |
| 税・その他 | 約3問 |
| 免除科目 | 5問 |
宅建士試験は全50問ですが、そのうち 20問 もが「宅建業法」から出題されます。つまり、試験全体の40%を占める最重要科目です。
しかも「宅建業法」は出題範囲が狭く、学習内容も明確です。そのため、しっかり対策すれば誰でも高得点を狙いやすい分野といえます。
チェックポイント
宅建試験に合格している人のほとんどは「宅建業法」で取りこぼしするようなことはありません。最低でも20問中18問以上の正解を目指しましょう。
民法(権利関係)の重要性
宅建試験の「民法」は、毎年14問程度出題される「宅建業法」の次に出題数が多い科目です。試験に合格する為には必ず得点するべき科目であることは間違いありません。
民法の出題数を確認してみましょう。
| 科目 | 出題数 |
| 民法(権利関係) | 約14問 |
| 法令上の制限 | 約8問 |
| 宅建業法 | 約20問 |
| 税・その他 | 約3問 |
| 免除科目 | 5問 |
法律に馴染みがない人にとっては、非常に難しいと感じるかもしれませんが、試験合格を勝ち取るためには避けては通れない科目です。
チェックポイント
民法(権利関係)は試験全体の28%を占めています。民法で点数を取りこぼずと合格は厳しいものになります。

民法で得点できていない人は、もう一度、基礎知識をしっかりと身につけて勉強しましょう。
法令上の制限を「後回し」にしている

「法令上の制限」は、専門用語や制度の複雑さから、苦手意識を持つ受験者が非常に多い分野です。実際、日常生活では聞きなれない言葉や制度が多く登場し、理解に時間がかかるのは当然のことだと思います。
しかし、ここで一つ大事な事実をお伝えします。
「合格ライン」に達する受験者は、民法と宅建業法を“完璧”に仕上げてきている。
つまり、「民法+宅建業法の攻略」は、もはや合格の前提条件にすぎません。そのうえで、他の受験生と差をつけるには「法令上の制限」であと1~2点を積み上げられるかどうかがカギになります。
「出題数8問」だからこそ差がつく!
「法令上の制限」は、例年8問前後と出題数は少ないですが、重要論点が繰り返し出題される特徴があります。
つまり、出題傾向を押さえておけば、点を取りやすい狙い目科目とも言えます。
さらにこの科目は、ちょっとした表現の違いが正誤に関わるケースも多く、単なる暗記では通用しない応用力が試されます。
だからこそ、苦手な人が多い一方で、ここで得点できれば確実にライバルと差をつけることができます。。
チェックポイント
「民法」と「宅建業法」で合格ラインに乗るのは“当たり前”。差がつくのは「法令上の制限」であと1点を拾えるかどうか!

苦手だからといって「法令上の制限」から逃げてしまうと、それだけで大きなハンディを背負うことになります!
5点免除制度を利用していない
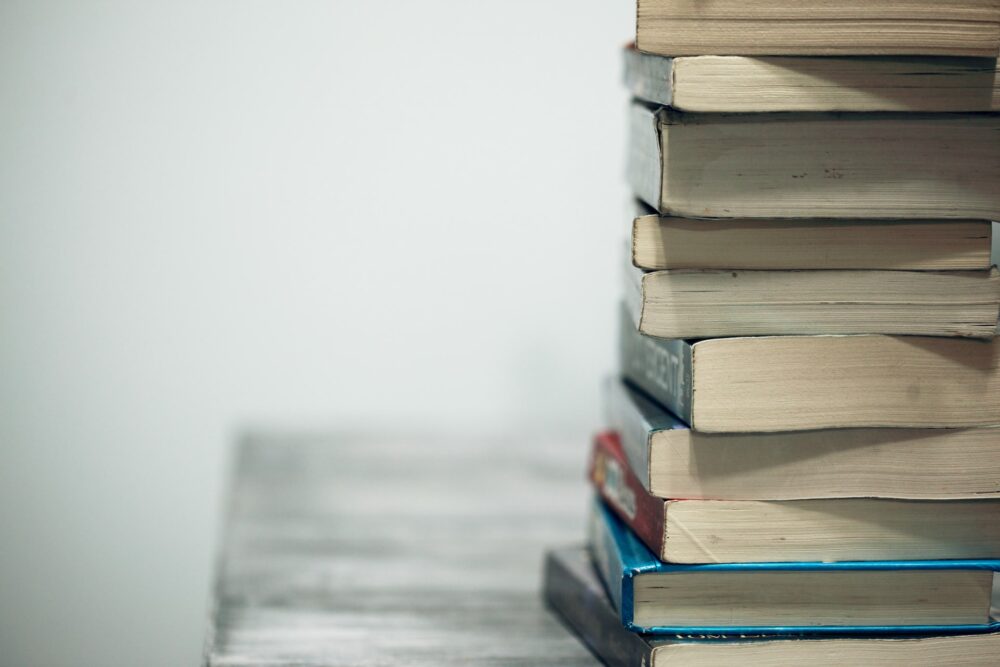
宅建試験の「5問免除制度」とは、宅建業に従事している人が、「登録講習」を受講することによって、「税その他」(問46~問50)が5問免除される制度です。
これにより、受験者は45問のみ解答すればよく、試験時間も通常より10分短い110分となります。
この制度を利用すると、以下のような2つの大きなメリットがあります。
- 免除科目の5問に関する勉強が不要になる。
- 通常の受験者よりも合格点が5点低くなる

5点免除が受けられる人は必ず受けた方がいい!
実は5点免除者は合格率が高い
本当に5点免除者は試験に有利になるのか?実は一般の受験者と5点免除者を比較してみると5点免除者の合格率が高くなっていることがわかります。
合格率の比較は以下の通りです。
| 実施年度 | 全体の合格率 | 一般の合格率 | 5点免除の合格率 |
| 令和元年 (2019年) | 17.0% | 15.2% | 22.9% |
| 令和2年 (2020年) | 16.8% | 16.0% | 19.4% |
| 令和3年 (2021年) | 17.7% | 16.7% | 21.3% |
| 令和4年 (2022年) | 17.0% | 17.0% | 17.3% |
| 令和5年 (2023年) | 17.2% | 15.3% | 24.1% |
| 令和6年 (2024年) | 18.6% | 17.8% | 21.9% |
以上のデータを見ると、5点免除制度は一般の受験者よりも有利であることに間違いありません。このことから5点免除を受けられるのであれば積極的に利用するべきでしょう。
チェックポイント
宅建試験はわずか1問の失点で合否が決定してしまう厳しい試験。5点免除を利用できる受験者はかなり有利になることは間違いない。

5点免除者の方が合格率が高い!
▶宅建とあわせて「賃貸不動産経営管理士」も狙っている人はこちらもおすすめです。ダブル受験のメリットや注意点を詳しく解説しています。👉 宅建士と賃管、どっちが難しい?資格の特徴を比較してリアルに解説
独学にこだわりすぎている

「宅建には独学で合格できる」とよく言われます。実際に独学で合格している人もいます。
でも、「なかなか点数が伸びない」「何年も受けてるのに合格できない」こうした悩みを抱える人の多くが、独学にこだわりすぎて、非効率な勉強を続けてしまっています。
独学にこだわる人が陥りやすい落とし穴は以下のとおりです。
- 出題傾向や狙われやすい論点がわからない
- 誤った理解を放置してしまう
- 苦手分野を避けてしまう
- 学習が孤独でモチベーションが続かない
- 試験に必要ないところまで無駄に学習してしまう

「頑張ってるのに報われない…」という状態は、本当にツラい。
宅建は出題者が「受からせないように」問題を作ってきます。だからこそ、出題の傾向・重要論点を的確に押さえた効率的な学習が必要なのです。
その点、通信講座を使えば
- 出題傾向をプロが分析済み
- 頻出論点をピンポイントで学べる
- 合格に必要な知識を短時間で習得できる
- 独学では気づきにくい盲点までカバーできる
- スケジュール管理やサポートで継続しやすい
「宅建に何度も落ちている」「今のやり方に不安がある」そんな人ほど、独学から一歩抜け出すタイミングかもしれません。

私は独学で3度失敗しました。
▶「もう独学では限界かも…」と感じた方は、私が実際に比較して選んだ講座を紹介しているこちらの記事も参考にしてください。👉宅建士通信講座の合格率を比較!初心者向けおすすめ4選
まとめ|“受かる気がしない”を今すぐ断ち切るために
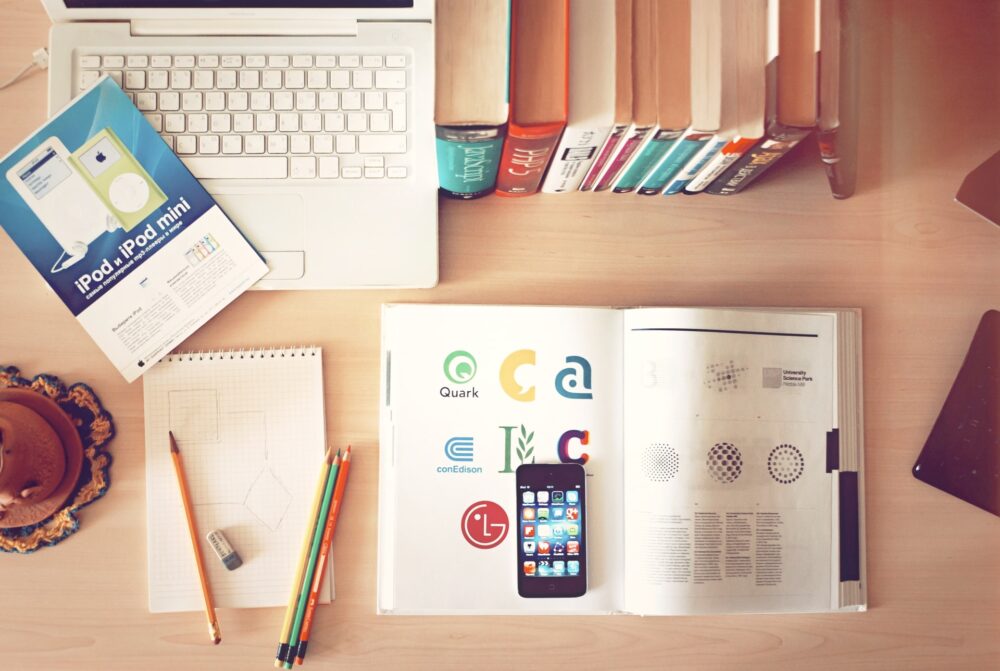
ここまで、宅建試験で「受かる気がしない」と感じてしまう原因や、失敗の共通点についてお伝えしてきました。
最後に、もう一度ポイントを整理します。
落ちる人の共通点
- 過去問を“理解”ではなく“暗記”で終わらせている
- 出題頻度を無視して、勉強の優先順位を間違えている
- 宅建業法と民法の攻略が不十分
- 法令上の制限などの苦手分野から逃げてしまっている
- 5点免除制度を使っていない
- 独学にこだわりすぎて、非効率な学習をしている
合格する人の共通点・行動
- 「宅建業法で8割以上」は絶対条件
- 「民法+宅建業法」だけでは不十分、法令上の制限も仕上げる
- 自分の苦手を知り、戦略的に対策する
- 通信講座などを活用して、効率よく合格レベルに達する
努力は裏切りません。ただし、間違った努力は平気で裏切ります。私は、3度の不合格を経て4回目でようやく合格できました。
もっと早く「落ちる人の共通点」に気づいていれば…と今でも悔しく思います。

「受かる気がしない…」と感じているあなたに、同じ後悔はしてほしくない!
次に読みたい記事
▶︎宅建は過去問だけじゃ無理?独学でつまずく人が知らない合格の本質を解説
→「過去問だけでいい?」に終止符。合格者がやってる本当の勉強法とは?
▶︎宅建士通信講座の合格率を比較!初心者向けおすすめ3選
→「どれがいいの?」を徹底比較。独学に限界を感じた人の救世主。
▶︎私が独学で宅建に挑戦した失敗談
→社会人が独学で宅建に挑戦したら、どれだけきついか?を解説