- 「宅建はハードルが高い…でも賃貸不動産経営管理士なら取れそう?」
- 「主婦や社会人でもスキマ時間で取れる資格って本当にある?」
- 「資格を取るなら将来性があるものにしたい!」
- 「賃貸不動産経営管理士ってどんな仕事に役立つの?」
近年、「賃貸不動産経営管理士(ちんかん)」という資格の注目度が急上昇しています。
特に2021年から国家資格化されたことにより社会人や主婦層から「キャリアアップ」「在宅ワークに活かしたい」「不動産業界で役立つ知識を身につけたい」という理由で受験する人が増加中です。
この記事では、賃貸不動産経営管理士の難易度・合格率・将来性について詳しく解説します。これから資格取得を目指す方にとって、学習の指針となる内容を提供します。

将来の自分に合った選択をしていきましょう。
賃貸不動産経営管理士とは?

賃管は賃貸物件管理のプロフェッショナル
賃貸不動産経営管理士とは、賃貸住宅の管理業務に必要な知識を有する専門家。国土交通省が推進する「賃貸住宅管理業法」において、一定の管理業務に対して設置が義務づけられている「業務管理者」になることができる国家資格です。

「業務管理者」になるためには「賃貸不動産経営管理士」または所定の要件を満たした「宅建士」であることが必要です。
そして、賃貸不動産経営管理士の主な役割は以下のとおりです。
- 賃貸借契約の適正化
- 入居者対応やクレーム管理
- 建物の維持・修繕提案
- オーナーとの信頼関係構築
宅建士が「契約前」の重要事項説明や賃貸契約を担当するのに対し、賃貸不動産経営管理士は「入居後」に発生する設備の管理や住民間のトラブル、オーナー対応などを担当します。
少子高齢化・持ち家離れが進む中で、賃貸ニーズの増加とともに、質の高い管理の需要も急拡大。入居者の安心だけでなく、オーナーにとっての資産価値の維持にも関わる重要な役割を果たしています。
今後の賃貸管理業界では重要なポジションとして期待されており、特に賃貸管理会社では社員に賃貸不動産経営管理士の取得を推奨する動きが広がっています。

業務管理者として登録できる賃貸不動産経営管理士の価値と需要は年々高まってきている!
難易度と合格率は?初心者でも狙える理由

過去の合格率から見る試験の現実
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格点 | 合格率 |
| 令和2年 (2020年) | 27,338名 | 8,146名 | 34点 | 29.8% |
| 令和3年 (2021年) | 32,459名 | 10,240名 | 40点 | 31.5% |
| 令和4年 (2022年) | 31,687名 | 8,774名 | 34点 | 27.7% |
| 令和5年 (2023年) | 28,299名 | 7,894名 | 36点 | 28.2% |
| 令和6年 (2024年) | 30,194名 | 7,282名 | 35点 | 24.1% |
合格率は毎年25〜27%前後で推移しています。不動産系の国家資格の中ではやや優しい部類に入るので、しっかりと対策すれば独学でも十分合格が狙える難易度だといえるでしょう。

ただ、2021年の国家資格化から難易度が年々上昇傾向にあるので、早めに合格していた方が良いかも。
出題範囲と対策のコツ
賃貸不動産経営管理士試験の出題範囲は以下の通りです。
試験科目 | 主な内容 |
管理受託契約に関する事項 | 管理受託契約の知識 |
管理業務として行う賃貸住宅の維持保全に関する事項 | 建物・設備の維持保全 |
家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項 | 金銭の管理実務 |
賃貸住宅の賃貸借に関する事項 | 賃貸借契約の実務 |
法に関する事項 | 法令知識 |
管理業務その他の賃貸住宅の管理の実務に関する事項 | その他の実務全般 |

試験はマークシート形式(50問120分)、1問1点。合格ラインはおおむね35点~40点(70〜80%)です。
独学でも合格可能か?
賃貸不動産経営管理士は独学でも合格は十分に可能です。ただし、合格するには高い正答率が求められます。
- 試験は 50問中35~40問前後の正解(70~80%) が合格ライン。
- 一見すると難易度は低めに見えるが、近年は制度改正や実務寄りの問題が増加傾向。
- 暗記だけでは対応できない「正確な知識」と理解が求められる。
- 出題範囲は「宅建よりも狭いが、法改正の影響を受けやすい」という特徴がある。
- 特に 民法改正や管理業法の新設など、最新情報のキャッチアップが不可欠。
そして、独学で挑戦する場合は以下の点に注意しておきましょう。
- 古い参考書を選ぶと法改正に対応できない。
- 学習のペースが自己管理になるため、モチベーションが維持しにくい。
- 重要ポイントを見落としやすい。
- 質問できる環境がないため、理解が浅くなる恐れ。

「独学でも行けるでしょ!」……そのノリで落ちてる人、実はめちゃくちゃ多いんです。
賃貸不動産経営管理士の将来性

なぜ今注目されているのか?
- 2021年から国家資格化 → 法的な価値と信頼性が大幅アップ
- 設置義務化により需要増 → 管理戸数が200戸を超える事業者に設置が必要
- 高齢化社会と空き家問題への対応 → 管理の質が問われる時代へ

今後、不動産業界だけでなく、地方自治体や管理会社、建設業界などでもニーズが広がる可能性があります。
資格取得によるメリット
- 宅建士と合わせて「ダブルライセンス」で差別化
- 転職市場でのアピールポイントに
- 将来的に「独立・開業」の道も開ける

特に賃貸物件の管理会社で活躍したい人におすすめです♪
宅建士との違いは?どちらを先に取るべき?

| 項目 | 宅建士 | 賃貸不動産経営管理士 |
| 難易度 | やや高め(合格率15〜17%) | やや易しめ(合格率25〜27%) |
| 法律知識 | 必須(民法・宅建業法など) | 必須(民法・借地借家法など) |
| 業務範囲 | 不動産取引 | 賃貸管理 |
| 独占業務 | 有(重要事項説明など) | 一部有(管理業法で設置義務) |
結論としては、「不動産取引」中心なら宅建士、「賃貸管理」重視なら賃貸不動産経営管理士が適しています。
もし、迷う方は宅建士から取得し、ステップアップとして賃貸不動産経営管理士を狙うことをおすすめします。
迷っている人はこちらもチェック⇒「宅建士と賃貸不動産経営管理士の特徴と向いている人を解説!」
忙しい社会人・主婦におすすめの勉強法
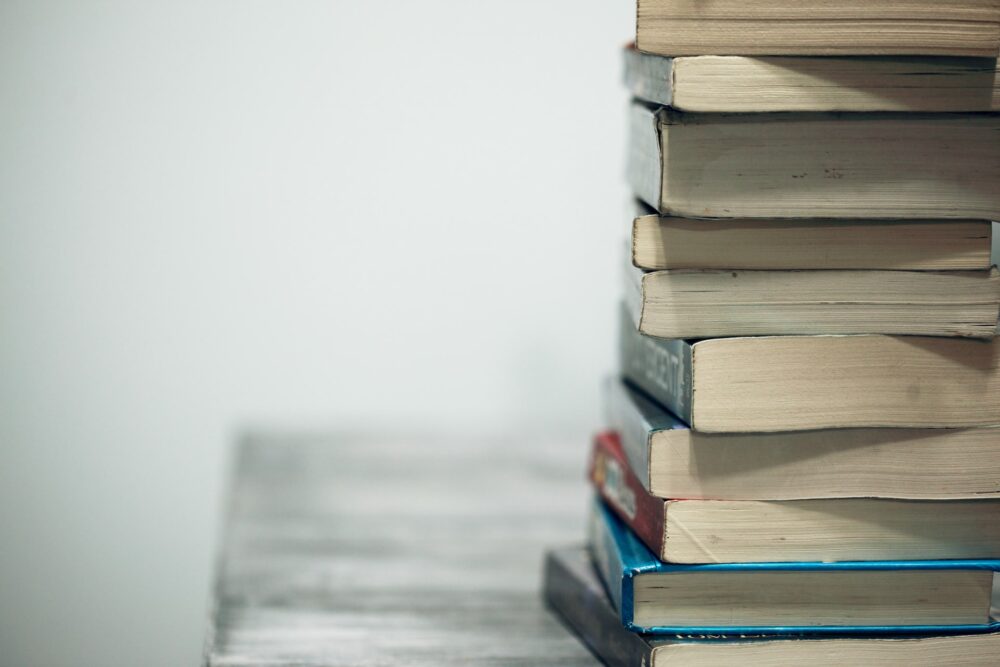
実際に賃貸不動産経営管理士は“独学でも合格できる資格”とよく言われます。確かに私も市販のテキストと過去問で合格をすることはできましたが、正直に言うとけっこうな時間をかけて勉強しました。
ここで少しだけ想像してみてください。
・「今日は疲れたから、また明日やろう」が積み重なる日々
・気づけば試験まで1か月。焦って詰め込み学習…
・自分のやり方が正しいのか、なんとなく不安なまま進めてしまう
独学には自由がある一方で、「正しい道筋が見えにくい」「誰にも確認できない」という落とし穴もあります。
そして、“少しの不安”があるだけで、行動のペースが緩んでしまうもの。
スキマ時間を最大活用するコツ
とはいえ、忙しい人にとって「まとまった勉強時間」を確保するのはかなり厳しいはず。だからこそ、「スキマ時間」をどう使うかがカギになります。
- 通勤中にスマホで講義を“聴く”だけ
- 洗濯物をたたみながら、耳でインプット
- 夕食後の10分で、アプリで○×クイズに挑戦
- 週末にまとめて問題演習

最初から「完璧を目指さない」。むしろ、「気軽に始められる」ことが、続けるための第一歩です。
通信講座のメリット
独学と通信講座はどちらもメリット・デメリットはあります。ただ、最近は「独学で失敗したあと、通信講座に切り替えて合格した」という声もよく耳にします。
実際に私も他不動産資格で何年も独学で失敗したしていたのに、通信講座に切り替えて合格できた経験があります。
- 学習スケジュールを自動で組んでくれる
- 法改正・出題傾向に即対応
- 出題傾向に沿った「無駄のない」カリキュラム
- 疑問点をすぐに質問できるサポート体制
つまり、「自分で悩む時間」をぐっと減らせる。これが結果的に時短と合格率を押し上げてくれました。
資格取得はゴールではなく、その先の将来を変えるための手段です。「何から始めればいいか分からない」と立ち止まるより、まずは行動しやすい方法を選んでみるのもひとつの選択です♪
▶ 迷ったときは、まず無料の資料請求から始めてみるのもおすすめです。
賃貸不動産経営管理士は「今こそ狙い目」の国家資格
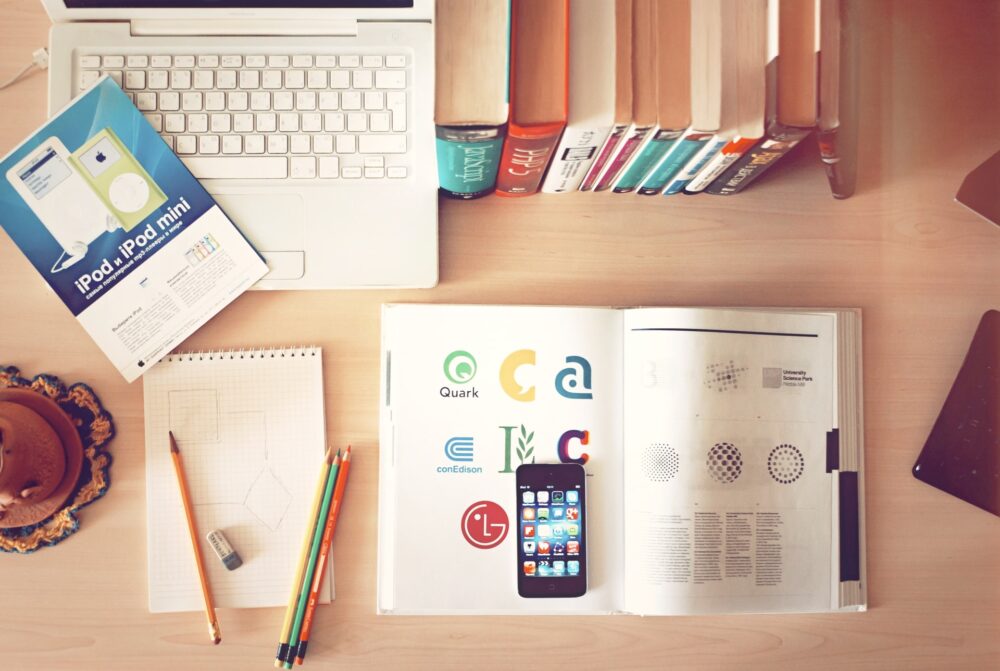
賃貸不動産経営管理士は、ただの“知識系資格”ではありません。国家資格としての信頼性に加え、賃貸市場の拡大と法改正による需要の増加という“追い風”が吹いています。
さらに、宅建士と比べて比較的手が届きやすい難易度でありながら、「業務管理者」への道も開かれるなど、将来性の高さは業界内でも注目の的です。
賃貸不動産経営管理士は、以下のような方に最適です。
- 宅建と合わせてスキルアップしたい人
- 未経験からの不動産業界チャレンジしたい人
- 賃貸管理の現場でキャリアを積みたい人
- 家事や仕事と両立しながら資格を取りたい人
国家資格化により、今後の将来性は非常に高く、合格率も比較的安定していることから、初心者でも狙いやすい資格です。
ただ、年々難易度が上昇していることには注意しましょう。未来を見据えて動き出すなら、「後回し」にせず、今がチャンスです。

最初の一歩は、「試験の情報を集めてみること」からでも十分です♪
次に読むべき記事はこちら